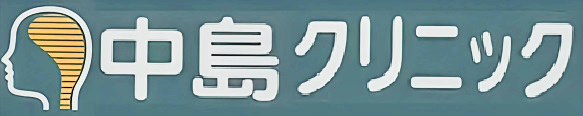私の三焦論(2)
解剖の進歩が変えた三焦の概念 中島クリニック 中島啓次
緒言
前回、大友一夫氏の論文「三焦」1)から以下のまとめを引用した。「胃からは、水穀の精微をしぼりとる二通りの「布状のもの」が出ており、それが上焦と中焦を表している。 腸管からは、やがて小便となるような水分を吸収する「布状のもの」が出ており、それを下焦と称している。したがって、上焦、中焦、下焦とも、腹腔内に存在する」。
腹腔内に存在するとした三焦が, 『中医基礎理論』(2)では胸腹腔を一つの中空の腑とし、その体腔すべてを三焦と考えている。また、『詳解・中医基礎理論』(3)では、「三焦は全身に行きわたっている組織間隙と細胞間隙に似て、これらは細胞外液が循行する通路である」としている。
この腹腔にあった三焦が全身に広がるといった「三焦の拡大解釈」はどのように発展して行ったのであろうか。解剖学の進歩が三焦の概念を変えていったと思う。この観点で、三焦の歴史をひも解いてみよう。
参考文献は主として山田慶児氏の『夜鳴く鳥』(4),『中国医学はいかにつくられたか』(5)『中国医学の起源』(6)とを参考にしている。それぞれの対応する文章は頁Pで表記した。
三焦の歴史
1.三焦膀胱の三焦(狭義の三焦)
三焦という語は紀元前90年頃の『史記』扁鵲伝にはじめて用いられ、「繵縁中經維絡.別下於三焦膀胱」と一続きで用いられていたという。陽気が「分かれて三焦膀胱に下る」と言うものである(4p182, 5p94, 6p414 )。このように三焦は,古くは膀胱と対で,膀胱三焦と記載されている。例えば、『霊枢・本藏第四十七』に以下の条文がある。
黄帝曰.願聞六府之應.岐伯荅曰.腎合三焦膀胱.三焦膀胱者.腠理毫毛其應.
黄帝曰.應之奈何.岐伯曰.腎應骨.密理厚皮者.三焦膀胱厚.粗理薄皮者.三焦膀胱薄.疏腠理者.三焦膀胱緩.
このように三焦と膀胱が対に併記されていたのは、初期の三焦は膀胱の上口にあり、循環する津液の調節作用、すなわち、尿を膀胱にためたり、排出したりする機能をもつものと考えられていたからである(4,5, 6,7)。
時を経て、三焦は上焦、下焦と分かれ、さらに中焦という言葉も加わり、現在の上焦・中焦・下焦になる。
古代でもおおまかな解剖は行われていた。狩猟で得た動物や家畜をさばいていただろうし、とくに動物の膀胱などは水筒の代用にも使用されている。膀胱を取り出すときにその表面に付着している腹膜を三焦と考えたのは無理もないと思われる。古代の稚拙な生理学では、食べたものが胃に入り、腸管を経て大便と小便にわかれ、小便は膀胱より出るが、その調節には膀胱上部に付着する腹膜、すなわち三焦が、関係していると考えても不思議ではない。
図1-Aを見ていただきたい。膀胱、直腸は後腹膜下にあり、膀胱表面を被っているのは腹膜である。膀胱の両側には、傍臍窩(the paravesical fossa)と名付けられた窪みが2つある。また、直腸と膀胱の間は直腸膀胱窩(女性では直腸子宮窩(ダグラス窩))がある。
図1-Bは摘出した膀胱である。膀胱前方には臍との繋がりの遺残である中臍靭帯があり、膀胱を吊り下げている。膀胱を上から見ると三角形で、膀胱上部にぴったりと被っている布状の腹膜を三焦と名付けたのではなかろうか。「三」は空の膀胱を上から見たら三角形、全体を見ると三面体だからであろうか。「焦」という言葉は炮ってちぢむという意味、藤同明保氏の「漢字語源辞典」によれば「鳥をあぶってチリチリと縮まる」ことを意味していた(1)。「膀胱は膨張する・広がる意味で、三焦は収縮する・ちぢむ。つまり膀胱に連続し反対の意味の「収縮すること」これが三焦の原義だろう。 機能的には、腸から三焦により尿が絞りだされて 膀胱にたまる。三焦がさらに膀胱をしぼって、排尿させる。つまり、初期の三焦は腸と膀胱に連続する排尿調節器官であったと言える(8)。
2.上焦・中焦の誕生
狭義の三焦から、どうして、上焦・中焦が生まれたのであろうか。
それを考えるには、『黄帝内経』をもう少し分析しなくてはならない。
2-1 黄帝内経の複雑さ
『黄帝内経』は、紀元前202年の前漢代に編纂され、『鍼経』と『素問』の2部構成で合計18巻と伝えられている。1部にあたる9巻を『鍼経』と呼び、2部の9巻を『素問』と呼ぶ。現存する『素問』は、762年に王冰によって編纂された。王冰はそれ以前の『素問』を大幅に変更したことがわかっており、王冰の『素問』からは古い『素問』を伺い知ることはできないと批判されている。『霊枢』は『素問』より新しい時代のもので、20年から200年ころ編纂された。『素問』より前に『鍼経』が編纂され、それが後に『霊枢』に引き継がれたと考えられている。『霊枢』は理論よりも診断・治療・針灸術など臨床医学に重点を置いている。古来は針灸術の経典とされ、『針経』とも呼ばれた(9)。
『黄帝内経』に集められた文章は一人が編纂したものではなく、どの点からみても、一概には論じられない多様性にみちている。書かれている理論や技術は多岐にわたる。何人もの手をへて現存する形をととのえた文章もあれば、一人で書いた文章もある。そのうえ、もとの文章を何篇かくっつけたり、いくつかに分断したり、分断したものを他の篇に挿入したり、といった操作を後世の編集者たちが唐代まで繰り返してきた。 一般に問答形式のほうが論述形式よりも著作年代が古いとされる。その門者と答者の組み合わせに1)雷公ー黄帝、2)黄帝ー少師、3)黄帝ー伯高 4)黄帝ー少愈、5)黄帝ー岐伯の五つがある。それぞれの答者を師と仰ぐ派閥を黄帝派、少師派、伯高派、少愈派、岐伯派とした。前漢の時代に活躍したのが黄帝派・少師派、新の時代が伯高派、後漢の時代は小愈派・岐伯派である(5,p74-75)(図2)。
この五派のうち最初に形成されたのは黄帝派であり、つづいて少師派が起こってくる。このいわば初期二派の説を受け継ぎ、発展させ乗り換えるかたちで、伯高派以下の後期三派が発展してくる。そのなかで主流派となったのは岐伯派である。他の二派はやがて吸収され、後漢の後半に理論と技術が統合されて単一の黄帝学派が生まれる。その段階で諸派の代表的な論文を集成して出来上がったのが、現存する『黄帝内経』であろうと 山田慶児氏は推測している(4,p74)。
初期の三焦は膀胱に連続する排尿調節器官であったのが、なぜ上焦・中焦とわかれたのか。それは、三焦の「三」を説明するために考えたのだろうか(7,p360)。そのための知識が、新の時代(AD8~16年)の医学研究の為の解剖で得られたのである。
2-2 新の時代の人体解剖
『漢書』王莽(おうもう)伝によると、その時の人体解剖は下記のようである。
「天鳳3年(AD16年)10月に反乱を起こした翟義(てきぎ)の徒党であった王孫慶が捕らえられたとき、新の皇帝・王莽は宮廷医や薬物療法担当医に命じて、動物の解体にすぐれた人物たちとともに、王孫慶を解剖させた(生体解剖の可能性もある)。五臓を計測し、竹ひごを使ってその脈の道すじをたどり、初めから終わりまでの経路を認知させて、これで病気を治療することができると宣言した。」。王莽の名をうけ、侍医たちが行った記録もしくは、それにもとづいて書かれたに違いない文章が『黄帝内経』に収録されている。いずれも伯高派の手になる『霊枢』の「骨度」・「腸胃」・「平人絶穀」の三篇である。したがって、これら三篇はAD16年、新の時代以降の記載ということができる(5, p88)。
この時の解剖は人体の硬部と軟部を問わず、すべてを計量し、人体を量的に認識しようとしていた。これを、山田氏は「計量解剖学」と呼んでいる(5, p89)。
2-3 伯高派の新しい三焦概念 上焦・下焦
伯高派はこの解剖を期に呼吸・消化・循環の生理学の構築にのりだしたのである。
前述したように『霊枢・平人絶穀第三十二』のなかの一遍に胃の構造と上焦・下焦の関係を明言している。
「胃は大きさ大一尺五寸、徑五寸、長さ二尺六寸、横に曲がっており、水と穀物三斗五升を納れる。その中はきまって穀物が二斗、水が一斗五升たまると一杯になる。
上焦は気を泄(おしだし)、その精微にして慓悍滑疾なるを出す。下焦は下へむけて 諸腸にそそぐ。・・・・・・」(5,p88)。
すなわち、上焦は胃の上口(噴門)より気をだし、胃の下口(幽門)より糟粕をだすのは下焦と考えていた。ここで始めて「上焦から気が出る」と述べたが、「衛気」という言葉はまだ表れていない。
2-4 衛気と営気
林 孝信 氏によると、「三焦」の概念が大きく変化するきっかけになったのは「営衛」の概念が医学に導入されてからのことである。「清濁」は胃の内部で消化されたものの性状であるが,「営衛」はそれから生成された精微な気としたのである(10)。
伯高派『霊枢・邪客第七十一』では、次のように述べられている。「胃の中でこなされた穀物は、宗気、津液と糟粕に分かれて、それぞれ3っのトンネルから送り出される。気体の宗気は肺で外から吸引した気と一緒に呼吸作用を行うとともに、さらに喉嚨をへて心脈を通り、循環作用の原動力となる。液体の津液からは、先ず素早く動く衛気が分かれてでてゆき、肌肉や皮膚のあいだに浸透して体中をめぐる。残りの津液は脈に流れ込んで血液に変化し、四肢を巡り五臓六腑にそそぐ、これが営気である。最後に胃の中に残った液体と固体にまじりあう糟粕は下へ、腸におくりこまれて消化され排出される (5, p95)」。
この時点では、心臓が循環の原動力とは認識せず、宗気がそれをになうものとした。尿の排出に関しては、腸から連続した膜が膀胱の上にあることより、これを三焦として尿生成器官、排尿調節器官として認識していたのは前述したとおりである。
2-5 兩焦という言葉の出現
伯高派は『霊枢・五味第五十六』において、上焦に代えて両焦という概念を導入してくる。
黄帝「営気と衛気はどのように運行するのか。」伯高曰「穀物は始め胃に入り、其の精微なるものは、先ず胃の 兩焦より出でて、以って五臓にそそぐ。別に出でてそれぞれ栄気と衛気の通路をめぐる。
黄帝曰.營衞之行奈何.伯高曰.穀始入于胃.其精微者.先出于胃.之兩焦.以漑五藏.別出兩行營衞之道.
この兩焦から、上焦と中焦が生まれようとしている。ここから新しい三焦概念が発達してくる。すなわち、伯高派の新説「兩焦」(『霊枢・五味第五十六』)をうけて、後漢の時代の「少兪派」が上焦・中焦という概念を整えたのである。
2-6 上焦・中焦の概念の出現
少兪派『霊枢・五味論第六十三』
「五味の口に入るや、各おの走るところあり、・・・・・・・・・・。
酸 胃に入れば、その気は澀(とどこお)りて以って収まり、之を両焦上ぐるも出入する能わず。・・・・・・・・・・・・
鹹 胃に入れば、其の気は登りて中焦に走り、脈に注ぐときは即ち血気之に走る。・・・・血脈は中焦の道なり。・・・・・・・・・・
辛 胃に入れば、其の気は上焦に走る。上焦は気を受けて諸陽を營(めぐら)すものなり。・・・・・・・・・・・・
苦 胃に入れば、五穀の気は皆苦に勝つ能わず、苦は下脘に入り、三焦の道は皆閉じて通ぜず。・・・・・・・・・・・・
甘 胃に入れば、其の気は弱小にして、上りて上焦に至る能わず。」
ここにいたって両焦は明確に分かれて上焦・中焦と呼ばれている(6,p417)。
さらに狭義の三焦を下焦と考え、広義の三焦の概念を発展させたのが、岐伯派である。
2-7 広義の三焦の誕生
岐伯派『霊枢・營衞生會第十八』につぎのように書かれている。
人は気を穀より受ける。穀は胃に入り、以って肺に伝与し、五臓六腑は皆以って気を受ける。其の清なるものを営といい、濁なるものを衛という。・・・・・・・・・・
営は中焦より出て、衛は上焦より出る。・・・・・・・・・・・
上焦は胃の上口より出て、咽に並(つらな)りて以って上り、・・・・・・。
中焦も亦た胃口に並(つらな)り、上焦の後に出る。・・・・・・・・・。
下焦は廻腸(闌門)より別れ、膀胱に注ぎてここに滲入す。
ついで、文末を「余は聞けり、上焦は霧の如く、中焦は漚(あわ)の如く、下焦は涜(みぞ)の如しとは、此れ之の謂(いう)なり」という黄帝の言葉で結んでいる。
以上、『黄帝内経』では上焦、中焦は胃にあり、それぞれ衛気と営気をだす。下焦は後腹膜にある。
つぎからは、横隔膜下にあった三焦が、いかにしてその制約から解き放たれ、横隔膜を越えるのかを考えたい。
3. 『黃帝八十一難經(難経)』の時代
難経の成立年代は、はっきり分かっていないが、『黄帝内経』成立より後であり、 また傷寒雑病論の張仲景が序で『八十一難経』を参考にしたと述べていることから]、それに先立つ著作である(11)。
『黄帝内経』の混沌とした、様々な文章を整理して「鍼灸医学の体系化」をしたのが難経である。『難経』における三焦の記載でもっとも重視されるのが、『二十五難』と『三十八難』の「三焦は有名而無形(名前はあっても形がない)」である。これが、後世で議論を巻き起こし、それぞれの時代で、それぞれの三焦論が展開されてきた。
《三十一難》には下記の記載がある。
「三焦は何を受けて生成されたのか。人体のどこから始まり、どこで終わるのか。
三焦は水穀の通路で、気機の活動に始終しているのである
上焦は 心臓の下の横隔膜、 胃の上口にある。 その治療点は膻中にあり、膻中穴の位置は玉堂穴の下一寸六分、両乳の問の陥没したところにあたる。
中焦は胃の中院にあり、その上でも下でもない。
その機能は水穀の消化作用で、治療点は臍のわきにある。
下焦の位置は臍下にあり、ちょうど膀胱の上口にあたる。
主に清濁の分別を司るため、専ら排出を主とし、受け入れの作用は無く、伝導機能を果たしている。治療には臍下一寸の所を用いる。これらを総称して三焦と呼ぶ。三焦の集合地は気街部にある」。
このように難経においては、上焦は心臓の下の横隔膜、 胃の上口にあるとされ、中焦は胃の中脘にあるとされ、下焦は膀胱の上口にあるとされている。
したがって、上焦は横隔膜を越えようとしているが、完全に越えて胸腔にはいたっていないのである。
4.後漢代(25-220)
後漢代になると、鍼灸医学だけでなく湯液療法も発展してきた。
この時代の代表的名医に華佗〔注:後漢の人:紀元208年に死去〕がいた。
華佗は鍼灸も湯液にも卓越しており、『中藏經』を著したとされる。しかし、
その文章内容から華佗の意思を受け継いだ弟子の呉晋または樊阿によって編集されたとする説が有力である(12)。 現存する最古のものは、元代の書家・趙孟頫ちょうもうふ(1254~1322)が著したものとされる(13)。したがって、『難経』に続く書物は『傷寒雑病論』とし、『中藏經』は元代と考え、後に考察することとする。
4-1『傷寒雑病論』
漢代の『傷寒雑病論』(AD150~219)は散逸してしまって、現在読める『傷寒雑病論』は晋の王叔和が撰次、宋の林億が校正し(1064年)、明の趙開美が1599年に校刻したものである。 したがって、三焦の拡大解釈の過程は現在の『傷寒雑病論』では追いきれない。
牧角和宏氏(14)によると唐代以前の医学を集大成した孫思邈(581~682年)が晩年編纂した『千金翼方』の中に「傷寒上」と「傷寒下」の二巻で構成される「傷寒門」がある。これを「唐時代の傷寒論」と考えると、この中に上焦の記載がある。
翼215(陽明63)陽明病,脅下硬滿,不大便而嘔,舌上白苔者,可與小柴胡湯。上焦得通,津液得,津液得下,胃氣因和,身濈然汗出而解(宋版傷寒論230条)。
陽明病,脇下硬滿し,大便せずして嘔し,舌上白苔の者は小柴胡湯をあたうべし。上焦通ずを得,津液下るを得,胃氣因りて和し,身濈然汗出て解す。
ここにおける「上焦得通」の文言は陽明の邪が膈に滲入し胃の上口(上焦)を塞いでいたのを小柴胡湯で邪を捌き、上焦を通じさせて、胃気が和し治癒に導いたものと考えられる。
翼224(陽明72)食榖欲嘔,屬陽明也,吳茱萸湯主之。得湯反劇者,屬上焦 也(宋版傷寒論243)。榖を食して嘔せんと欲するは、陽明に属する也,吳茱萸湯主之。湯を得て得反して劇しき者,上焦に屬する 也。
この文も呉茱萸湯が効かない場合は、邪が膈にあり、上焦(胃が横隔膜を貫く上口)にあると述べている。上記2条の上焦が胸腔とするとつじつまが会わない。つまり、唐時代の傷寒論では上焦は横隔膜内の胃の上口にあるのである。しかし、牧角和宏氏によると、今日に伝えられた『千金翼方』は、またもや北宋の林億らの新校正を経たものであるという。上記2条は『宋版傷寒論』にも同じ記載がある。これらは、漢時代の傷寒論からの記載か、林億の追記したものであろうか。
またもや、胃の上口にあった上焦が横隔膜を超えて胸部に至った時代が判然としないのである。
4-2『金匱要略』
一方、『金匱要略』では、上焦は肺の病とされている。しかし、不完全な問答形式で、傷寒論の文体と異なるので、後漢の時代ではないと思われる。『金匱要略‧五臟風寒積聚病脈並治第十一』師曰:熱在上焦者,因咳為肺痿;熱在中焦者,則為堅;熱在下焦者,則尿血,亦令淋秘不通。大腸有寒者,多鶩溏;有熱者,便腸垢小腸有寒者,其人下重便血;有熱者,必痔。
《金匱要略‧臟腑經絡先後病脈證第一》師曰:吸而微數,其病在中焦;實也,當下之即愈;虛者,不治。在上焦者,其吸促;在下焦者,其吸遠;此皆難治。呼吸動搖振振者,不治。
寺澤捷年氏によると、「『傷寒論』では三焦は腹腔内にあり、『金匱要略』の多くの条文は三焦の機能不全による結果を記したものであり、三焦の存在部位を示していない」と論説している(15)。
上焦が横隔膜を越えるのは、さらなる新しい解剖学による知見を待たなければならない。 1千年の時間をへて、新代(AD16年)の計量的な解剖学から宋代(1045年)に記述的解剖学が始まった。新代の計量的な解剖学というのは、前述したように解剖の主眼を、臓器の大きさや容量、経絡(血管)の長さの記述においており、横隔膜によって胸腔と腹腔が分けられていることも眼中にないのである。胸腔の概念がないのに、今の上焦の概念は生まれてこない。
繰り返しになるが、後漢までは、上焦は 心臓の下の横隔膜、 胃の上口にあるとされる。
5.宋代の人体解剖(1045年)
1045年(宋慶曆5年)、反乱軍の歐希范とその部下243人が環州西門の外で捕らえられ殺された。 当時の宜州奉行であった呉簡が画家の宋景を組織し、宮廷で処刑された歐希范等の遺体56体を解剖させ、臓腑の位置を観察して図を描かせたものが『歐希范五臟圖』である。 原書は失われている。
この図は主に人体の内臓の地図であり、肝臓、腎臓、心臓、大網の解剖学的位置と形状はおおむね正しい。 例えば、肺の下には心臓、肝臓、胆嚢、脾臓があり、胃の下には小腸、次に大腸、大腸の隣には膀胱がある……腎臓は2つあり、1つは肝臓の右側に、もう1つは脾臓の左側にある、といった具合である。 例えば、「蒙干(反乱軍の一人)はよく咳を病み、肺も胆嚢も黒く、歐銓(反乱軍の一人)はめったに目を病まず、肝臓には白い斑点がある」といった病理学的見地からの観察もあった。
しかし、歴史的な制約から、呉簡の論考には、「咽喉には3つの口があり、1つは食、1つは水、1つは気」、「心臓にも口がある」、「肝臓は切片の数が違う」などという誤解が残っており、これらは偏った観察によるものと思われる(6,p377-379)。
もう一つの人体解剖が崇寧年間(1102年–1106年)に行われ、楊介が罪人を解剖して描いた『存真図』がある。こちらも現存しないが、一部が元代の『玄門脈内照図』に写され、現在まで伝わっている(図3)(16)。
このなかの「心氣圖」には、右側胸郭と胸腔の主脈関係を描いており、「気海隔膜」では気海と隔膜(横隔膜)、胃上口、脾経、肝経、腎経の肝経を描いている17)。
したがって、この時代では横隔膜が胸腔と腹腔を分けているのを認識し、気海すなわち、宗気の積もる所が胸腔内にあることが見て取れる。
一方、西洋においては、実際に人体解剖がおこなわれ、記述されたのは1316年で中国より250年遅れている。イタリアのモンディーノ・デルッツィの著書『アノトミア』(1316年に書かれたが、1478年まで印刷されなかった)が西洋での最初の解剖図である。千年以上昔のギリシア時代のガレノスと同様モンディーノは、脾臓は胃に内容物を送り、肝臓は五葉からなり、心臓は三っつの心室を持っていて、子宮は複数で成っている、と間違った記述をしている。
さて、世界に先駆けて行われた宋代の解剖のあと、三焦の概念はどのように変わったのか、宋時代以降の三焦の記述を見てみよう。
6. 金時代(1115~1234)
『三因極一病證方論(三因方)』
陳言(無澤)は1174年に『三因極一病證方論(三因方)』著したが、その中で、三焦の形は『手掌大ほどの脂膜である、まさに膀胱と相対して存在し、その中から二本の白い脈が中から出ており、その一つは脊を挟んで上り、脳を貫いている。上焦は膻中に、中焦は中脘に、下焦は臍下の腎間の動気にある』。と述べている。陳氏曰:“三焦者,有脂膜如手大,正與膀胱相對,有二白脈自中出夾脊而上貫於在脳。・・・・・上焦在膻中,內應心; 中焦 在中脘,內應脾; 下焦 在臍下,即腎間動氣,分佈人身,有上中下之異。
7. 元代(1279-1367)
7-1 『難経本旨』
元代の袁坤厚(えんこんこう)は『難経本旨』で三焦の臓腑間隙説を著わしている。
「いわゆる三焦とは、隔膜の脂膏の内側、五臓六腑の間隙にあり、水穀が流れ化する関鍵となっており、その気はその間に融合しており、隔膜を薫蒸して、発して皮膚分肉の間に達し、四傍を運行してる。上中下と言われているのは、そのそれぞれが存在している位置によって呼ばれたものです。まことに原気の別使そのもののありようです。ですからそこに形がないといっても、内外の形によって形づけられ、その実体はないといっても、内外の実体に沿うことによって形づけられているのです。』として、三焦には形はないといっても、腹腔内の臓腑の間の部位がこれにあたると臟腑間隙說をとなえた。 三焦は五臓六腑の間隙にあり、皮膚分肉間の全身を巡っている。
前述したように『中藏經』の現存する最古のものは、元代の書家・趙孟頫(1254~1322)が著したものとされているので、ここで解説する。
7-2 『中藏經』
『中藏經』の中に次のような有名な三焦についての記載があるが、元代の袁坤厚の『難経本旨』の趣旨と同様である。
「三焦は人の三元の気であり、中清の府と言われている。五臓六腑・営衛経絡・内外左右上下の気を総領している。三焦を通じて、すぐに内外左右上下にすべてが通じて、全身を灌漑し、内外を調和させ、左より右へ、上から下へと導き、これより大きいものはない。別名を玉海、水道と呼ばれている」(論三焦虛實寒熱生死逆順脈證之法第三十二)。この文章は現代の「三焦は間質液の流れ」という考えそのものであり、後漢の華佗や、その弟子たちが書いたものではなく、元代の人が書いたものと思われる。無名の人が書いたものに箔をつけるために、華佗が書いたものとして発表したたのであろうか。
宋代の人体解剖を経て、金代の『三因方』、元代の袁坤厚の『難経本旨』、趙孟頫の『中藏經』で初めて、上焦は横隔膜を越えているようだ。しかし、実際はそれぞれの病態の位置をしめしているにすぎない。
8 明代(1368~1661)
虞摶(ぐたん)(1438~1517)は1515年『医学正伝・医学或問』で、『三焦は腔子を指している言葉で、胃腸がつかさどる場所すべてを包括している。胸中の横隔膜(肓膜)の上を上焦、横隔膜の下から臍までを中焦、臍下を下焦とし、総じて三焦と名づけている。その本体は、腔子の中の脂膜にあたり、五臓六腑の外側をすべて網羅している』と述べている。
9 清代末期
十九世紀,中国に西洋医学が流入したことによって,中国伝統医学には,さまざまな変化が生じた。当時の医師たちは西洋の解剖学・生理学に三焦に相当する用語を見つけようとした。その考え方は現代にまで及んでいる。
10 現代
現代においては、共焦点レーザー内視鏡ならびにMRIなどの先端医療機器が、生きたままの生体そのものを観察することができ、新しい解剖学、組織学が発展している。
前号で解説したように、2000年の時を経て三焦が再び、我々の前に現れたのである。2018年3月27日、ニューヨーク大学の研究チームが人体最大の器官を新たに発見したと、科学誌『Scientific Reports』に発表した(14)。それは、間質(Interstitium)という名前であるが、『中藏經』が言うところの三焦そのものではないだろうか。
考察
三焦こそが中国医学の生理学の出発点となった概念であり、またその生理学を特徴づけているものである(5,p94)。 その時代、時代の解剖学、生理学の知識が三焦の概念を変えてきたのであろう。
膀胱の上口にあった狭義の三焦はいかにして、全身に広がっていったのであろうか。それは、医学の発展の基礎である人体解剖の発展によるものと思われる。
古代の解剖による「狭義の三焦」
家畜とか狩猟でえた獲物を解剖すると膀胱に尿が貯められ、排出されるのは分かった。食べた水穀が胃を通り、小腸、大腸をへて肛門から便が出て、膀胱・尿道から尿が分かれて出るはわからなかった。初期の考えでは小腸と大腸の境目である廻腸を闌門と称し、大便と小便を分ける部位だと考えた。水筒の目的で動物から膀胱を取り出す際、膀胱表面の腹膜が直腸と連続していることより、この腹膜が水分を膀胱に浸透させるだけでなく、排尿を調整する器官と推定したのではないだろうか。取り出した腹膜が着いたままの膀胱は、その形が三角形で、あぶった鶏肉のようである。表面のちぢれた腹膜を「三焦」と命名し、全身を巡る津液の調節器官と考えたのであろう。いわゆる「三焦膀胱」という狭義の三焦である。時をへて、三焦の意味が分からず、試行錯誤が生まれた。特に三という意味が分からず、3つの焦(上焦、中焦、下焦)を探すようになった。散発的な解剖から、医学目的の人体解剖が新代に起こり、三焦の意味も深まってゆく。
AD16年、新代の人体解剖以後の三焦
黄帝内経の三焦
天鳳3年(AD16年)新の皇帝・王莽は反逆者の王孫慶を解剖させた。
これを契機に『黄帝内経』の伯高派は呼吸・消化・循環の生理学の構築にのりだした。『霊枢・平人絶穀第三十二』のなかの一遍に胃の構造と上焦・下焦の関係を明言している。 「上焦は気を泄(おしだし)、その精微にして慓悍滑疾なるを出す。下焦は下へむけて 諸腸にそそぐ。・・・・・・」
さらに論をすすめ、『霊枢・邪客第七十一』で、上焦から衛気と営気が出て、衛気は肌肉や皮膚のあいだに浸透して体中をめぐる。営気は脈に流れ込んで血液に変化し、四肢を巡り五臓六腑にそそぐ。最後に胃の中に残った液体と固体に混じりあう糟粕は下の腸におくりこまれ、下焦で処理される。
伯高派は『霊枢・五味第五十六』において、上焦に代えて両焦という概念を導入してくる。伯高曰「穀物は始め胃に入り、其の精微なるものは、先ず胃の 兩焦より出でて、以って五臓にそそぐ。別に出でてそれぞれ栄気と衛気の通路をめぐる。
後漢の少兪派『霊枢・五味論第六十三』はこの「両焦」を上焦・中焦と呼ぶことになる4,p417)。
最後に、後漢の岐伯派が狭義の三焦を下焦と考え、広義の三焦の概念を発展させた。『霊枢・營衞生會第十八』で次のように結論づけている。
「人は気を水穀より受ける。水穀は胃に入り、以って肺に伝与し、五臓六腑は皆以って気を受ける。其の清なるものを営といい、濁なるものを衛という。・・・・・・・・・・
営は中焦より出て、衛は上焦より出る。・・・・・・・・・・・
上焦は胃の上口より出て、咽に並(つらな)りて以って上り、・・・・・・。
中焦も亦た胃口に並(つらな)り、上焦の後に出る。・・・・・・・・・。
下焦は廻腸(闌門)より別れ、膀胱に注ぎてここに滲入す。」
以上より、三焦は食物の通路であり、胃で消化された食物より「気」が産生される。
胃の上口より上焦の気(衛気)が全身を巡る。胃の中脘より中焦の気(営気)が脈管を通じて全身を巡る。下焦は膀胱の上口にあり、すべての水をさばくのである。
これが、膀胱の上口にあった狭義の三焦が新代の人体解剖をへて広義の三焦となった経過である。黄帝内経の三焦は腹腔内にあり、横隔膜を越えていない。しかし、上焦の衛気は横隔膜を越えて、胸腔内より、全身に散布されることを忘れてはならない。また、胃の重要性、胃が水穀を消化し気(衛気・営気)を作り出すことも強調されなければならない。
江部洋一郎氏が『経方医学』19)において、胃気の重要性を強調していたのが理解できる。
1045年、宋の人体解剖以後の三焦
宋の人体解剖をへて、陳言(無澤)は1174年に『三因極一病證方論(三因方)』著した。その中で、「三焦は手掌の大きさほどの脂膜である。まさに膀胱と相対して存在し、その中から二本の白い脈が出ており、その一つは脊を挟んで上り、脳を貫いている。」とのべている。まさに人体解剖を見ないと書けない描写である。
現代医学的にみると、二本の白い脈の一つが脊柱を挟んで上りとあるのは胸管と思われる。胸管はリンパ本幹の最大のものであり、乳び槽より始まり、腹腔内を上行し横隔膜の大動脈裂孔より胸腔内にはいる。胸腔内では正中右側を上行した後に、第五胸椎の高さで正中左側へ移行し、左静脈各に流入する。さすがに、当時の解剖ではここまで追うことはできないが、後世の人が、三焦はリンパ系であると考えた原型がここにあると考える。
しかし、陳言(無澤)は「上焦は膻中に、中焦は中脘に、下焦は臍下の腎間の動気にある」と述べている。はたして、上焦は横隔膜を越えて胸腔に達したのであろうか。これは三焦の位置をのべているのではなく、三焦からでる気の話である。宋代の『存真図』では横隔膜が胸腔と腹腔を分けているのを認識し、気海すなわち、宗気の積もる所が胸腔内にあることが見て取れる(図4)。しかし、上焦の位置が胸腔にあるのではなく、その「気」が胸腔に溜まっているということである。
三焦の場所と気の誤解 身体の場所を表す区分としての三焦
上焦、中焦が存在する場所は胃であり、上焦の気は胃が横隔膜を貫通する上口より胸にでる。中焦の気は胃の中脘より、脈中にはいる、下焦は狭義の三焦であり、膀胱の上口にある。
「三焦」が存在する場所とその機能である「気」が及ぶ場所を混同する傾向がある。
『脈経』は、中国医学古典の一つであり、晋代の王叔和による脈診書である。完成年代は不明であるが、266年から282年の間らしい(12)。このなかの「五臓六腑陰陽逆順」で、王叔和は「心部合於上焦」、「肝部合於中焦」、「腎部合於下焦」と述べている。また、唐代の王冰(生年・没年ともに不詳)は『素問』「金匱真言論篇」の注釈で次の様に述べている。「心と肺は上焦に位置する。肝と脾は中焦に位置する。そして、腎は下焦に位置する」。
すなわち、晋代、唐代においては、身体の上中下の区分を上焦中焦下焦の名で表している。すなわち、上中下三焦の名は部位そのものの名前になったのである(7, p337)。
有名無形の誤解
『難経』の「二十五難」と「三十八難」で「三焦は有名而無形(名前はあっても形がない)」としている。これが、後世で議論を巻き起こし、それぞれの時代で、それぞれの三焦論が展開されてきた。
まず、強調したいのは『難経』は鍼灸の書である。鍼灸の原理は流れる「気」で成り立っている。「気は有名而無形」である。したがって、気を作り出す三焦は、「有名而無形」なのである。
もっとも、科学の進歩によって、見えない素粒子ニュートリノがを実験装置「カミオカンデ」で観測されたように、気も科学の進歩により観察されれば気も「有名而有形」となるであろうか。
全身の結合織間ネッワークである「間質Interstitium」の流れも、いままで見えていなかったが、科学の進歩、解剖学の進歩により見えるようになったのである(18)。
最後に、中国医学における三焦の意義を理解するには、『素問‧靈蘭秘典論第八』の「三焦者.決涜之官.水道出焉」を深読みしなければならない。
古来中国では人体の統御を国家のそれに例えることが多い。官僚制になぞらえて、物のあいだのの関係や作用をとらえようとするのは、中国医学のいちじるしい特徴だといってよい。さらに言えば、中国の官僚制は水利灌漑の管理組織からうまれたという説もある(5-p99)。
夏朝(紀元前1900年頃)の創始である禹皇帝は黄河の治水を成功させたという伝説上の人物である(20)。黄河、長江の大河のほか無数の河が走る中国はもともと水害が多い国であり、治水で国家指導者の能力が試されてきた国でもあった。中国の皇帝が竜の紋章を使うのは、竜が治水の象徴だからだ。 禹皇帝は治水の神様とも言われた。古代より暴れる竜のような黄河の氾濫で人民を苦しめていた洪水を堤防で防ぐだけではなく、運河を作り水を流す治水を行なったのである。これを「決瀆」と言い、まさに三焦は体の治水を意味するのである。すなわち、病は水害と同じように考えたのだろう。病を治すのは、水のコントロールが重要であると考えたのである。古代中国では、人体は心血管系よりも、水系モデルが主流になっていった。
2023年7月28日台風5号はに福建省に上陸、その後北上し、北京、天津、河北地域で連日の豪雨災害をもたらした。全国で300万人の被災者をだし、過去600年冠水したことがなかった故宮・紫禁城も水に浸かった。時の国家主席は皇帝といえるだろうか。
水系モデル
中国医学の身体像は水系モデルといえる(図6)。
身体を縦に12の主要な河川の経脈が走り、その間をいくつもの支流を結んでいる。中央には水穀(飲食物)を輸送する大河が口から肛門まで貫通し、その中間に水穀の海と称するダムの胃が横たわっている。胃でこなされた水穀は、分かれて栄衛の気となる。衛気は上流側の出口である上焦から出て皮膚や肌肉の間に浸透し、全身を湿原のようにひたす。営気はもう一つ出口である中焦から出て脈に流れ込み、血液となって全身を循環し、臓腑に注ぐ。糟粕は下の出口から小腸に送られて消化され、大腸にでて固形となり排出される。水液のほうは下焦をへて膀胱に送られ排出される。宗気は肺に蓄えられ、呼吸運動をおこない、血液を循環させる。全身をめぐった栄衛の気はふたたび胃に還流し、水穀と一緒に処理される(5-p98-99)。
古代中国では人体を自然と比較して考える。人間の病気の一つは、水害と同じように水がコントロールできなくておこると考えた。上記の水系モデルで洪水が起こるとき、水門を空けることで、水を放出して村や都市を救う。この権限を持つ役人が「決瀆之官」である。人間においては三焦がこの役割を果たすのだ。全身をめぐる水と気
を制御するのが三焦の役割である。
結語
三焦は名はあるが、形は今はない。しかしその機能はある。
三焦の本態は次の3つである。
1. 水穀を胃で消化し気(宗気・衛気・営気)を生み出す(胃気の重要性)。
2. 水と気(血管内の営気も含む)を皮膚と内臓を含む全身に巡らせ、制御する(水 系モデル)。
3. 身体を上焦、中焦、下焦に区分けすることは意味がない。身体の上中下の区分を上焦中焦下焦の名で表しているにすぎない。
文献
1) 大友一夫.三焦.東静漢方研究室 1980;4(6):1-13.
2) 浅野 周 全訳中医基礎理論 (中医薬大学全国共通教材) たにぐち書店 東京 200年8月 p132-135
3) 劉 燕池 (著) 詳解・中医基礎理論 東洋学術出版社 千葉 1997 p92
4) 山田慶兒 『夜鳴く鳥』 岩波書店〈岩波書店〉、P94、1990年5月30日年
5) 山田慶兒 『中国医学はいかにつくられたか』 岩波書店〈岩波新書〉、P94、1999
年 1月20日
6) 山田慶兒 『中国医学の起源』 岩波書店〈岩波書店〉、P414-420、1999年7月28日
年。
7)金関丈夫 日本民族の起源(三焦)法政大学出版局、東京、p353-355、1976
8) 林 孝信『素問』『霊枢』における三焦概念の変遷 日本医史学雑誌 第 56 巻第 2 号(2010)
9) https://ja.wikipedia.org/wiki/黄帝内経
10)林 孝信 営衛と両焦 ―三焦概念の変遷についての考察― 日本医史学雑誌 第 59 巻第 2 号(2013)
11) https://ja.wikipedia.org/wiki/難経
12) 傅 維康 (著), 川井 正久 (訳) 中国医学の歴史 東洋学術出版 市川 1997 p194
13)https://zh.wikipedia.org/zh-tw/华氏中藏经
14)牧角和宏 傷寒論の検討:各論Ⅲー『千金翼方』に引用された傷寒論 各論Ⅲの(1)ー『千金翼方』巻九全文と解説 福岡県医師会研究会会報 第30号・3号 p42 2009
15) 寺澤捷年. 『傷寒論』『金匱要略』における「三焦」と腹部動脈による三区分の提案. 日東医誌 2019; 70: 77-81.
16)https://ja.wikipedia.org/wiki/宋_(王朝)
17)京都大学貴重資料デジタルアーカイブhttps://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00002326#?c=0&m=0&s=0&cv=16&r=0&xywh=-3237%2C0%2C12088%2C3743
18)Benias, P. C. et al. Structure and distribution of an unrecognized interstitium in human tissues. Sci. Rep. 8, 4947 (2018).
19)江部洋一郎、横田静夫 『経方医学1』第3版 p29 2011年
20) https://ja.wikipedia.org/wiki/禹