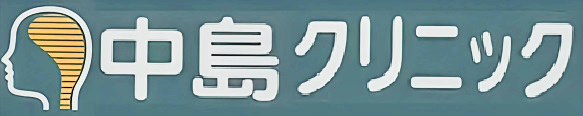緒言
三焦こそ中国医学の生理学の出発点となった概念であり、またその生理学を特徴づけているものである1)。その時代、時代の解剖学、生理学の知識が三焦の概念を変えてきた。中医薬大学全国共通教材とされる『中医基礎理論』では三焦は次のようにまとめられている。 「三焦とは上焦、中焦、下焦の総称で、やはり六腑のひとつである。三焦の具体的な概念は明確でないが、三焦の生理機能については、気の管理と水道を通行させることで一致している。その実態を現在の学者は、胸腹腔を一つの中空の腑とし、その体腔すべてを三焦と考えている。人体の臓腑のうち最大のものだから「狐府」と呼んでいる」2)。
大学院クラスの学生が必ず学習するテキストとされる『詳解・中医基礎理論』では、次のようにも述べられている。
「現代医学の視点からとらえると,三焦は全身に行きわたっている組織間隙と細胞間隙に似ている。これらは細胞外液が循行する通路である。細胞外液の循行代謝によって細胞に新陳代謝において必要となる酸素・栄養物質・酵素・水・塩類・ホルモンなどが供給され,細胞内の代謝過程で産生される不要物が,この間隙を通って排泄器官に運ばれ体外に排出される」3)。
2000年の時を経て三焦が再び、我々の前に現れた。2018年3月27日、ニューヨーク大学の研究チームが人体最大の器官を新たに発見したと、科学誌『Scientific Reports』に発表したのである。それは、三焦という名前ではなく間質(Interstitium)であった。
「間質の発見」は研究チームが、超高性能の内視鏡で胆道を観察していると、粘膜下に体液が流れる組織を偶然見つけたことに端を発する。組織標本にすると、そこは従来通りの単なる結合組織だが、生きたままの組織で観察すると、体液を満たしたその間質は認められた。それは真皮にも認められ、消化管や気管支、膀胱そして、動脈や静脈、筋膜を囲んだりしている層にも確認できた4)。
2021年にもニューヨーク大学のグループが間質に関する続編を発表した。
2018年に発表した論文では、間質空間が体内で連続しているのか、それとも個々の臓器内に限定されて不連続なのかは、依然として不明であった。
今回、彼らは2つのアプローチで「間質空間の連続性」を示す証拠を示したのである5)。
一方、『黄帝内経』を生んだ中国でも経済力の発展とともに、有名無形であるものも見とおす力を得た。 間質液が体全体を流れること、経絡の存在、これらを証明すべく研究している。特に2006年以降、北京グループは、間質液の輸送に関する一連の研究成果を発表してきた6)。
現代医学は、血液循環に関しては、その解剖生理ならびにその病態・治療では、東洋医学のそれをはるかに凌駕している。しかし、リンパ系、間質液の流れに関しては研究途上である。
「三焦は間質である」という仮説を議論する前に、三焦の歴史を振り返る必要がある。
三焦の歴史
1.『黃帝内經』
三焦という言葉が初めて使われたのは、古来より医学の聖典とされてきた『黄帝内経』である。したがって、先ずは『内経』の記載から三焦を考えるのが基本である。
今から、43年も前に大友一夫氏が.三焦についての論文を書かれている7)。 大友氏は次のようにまとめている。
「三焦の形、語源、位置に関し、古書に則って考察を加えてきたが、それらを整理すると、以下の如きものが想定されてくる。胃からは、水穀の精微をしぼりとる二通りの「布状のもの」が出ており、それが上焦と中焦を表している。 腸管からは、やがて小便となるような水分を吸収する「布状のもの」が出ており、それを下焦と称している。
したがって、上焦、中焦、下焦とも、横隔膜下に存在する」。
この「布上のもの」は現代医学的にみると臓側腹膜が合わさった間膜としている。
これらははちょうど、上焦(前胃間膜)と中焦(後胃間膜)の二つの焦が、胃から別れて出ながら、胃横隔膜間膜で移行し合い膈を貫くということと対応している(図1)。又、これらの間膜は、後腹膜を介して、当然膀胱ともつながっている。
図1
最近では、寺沢捷年氏は「腸間膜が一つの臓器である」というCofferyの説を基に大友説を世に広く紹介し支持した8)。
黄帝内経の複雑さ
黄帝内経は何よりもまず鍼灸医学の書であったことを忘れてはならない。。
『素問』の81篇中直接に鍼灸にかかわる内容を記述した篇は32編で『霊枢』では81篇中49篇である。
また『黄帝内経』に集められた文章は一人が編纂したものではなく、どの点からみても、一概には論じられない多様さにみちている。書かれている理論や技術は多岐にわたる。一般に問答形式のほうが論述形式よりも著作年代が古いと思われる、何人もの手をへて現存する形をととのえた文章もあれば、一人で書いた文章もある。そのうえ、もとの文章を何篇かくっつけたり、いくつかに分断したり、分断したものを他の篇に挿入したり、といった操作を後世の編集者たちが唐代まで繰り返してきた。その過程で三焦という概念も変わってきたのである1)。
- 『黃帝八十一難經』(『難経』)
『黄帝内経』の混沌とした、様々な文章を整理して「鍼灸医学の体系化」をしたのが難経である。『難経』における三焦の記載でもっとも重視されるのが、『二十五難』と『三十八難』の「三焦は有名而無形(名前はあっても形がない)」である。これが、
後世で議論を巻き起こし、それぞれの時代で、それぞれの三焦論が展開されてきた。
いずれにしても、黄帝内経と難経による三焦の共通認識は次の4つである。
1. 水の通路である。
2. 気の通路である。
3. 内臓と密に関連を持つ
4. 皮膚と内臓と密に関連を持つ
3.漢代
漢代になると、鍼灸医学だけでなく湯液療法も発展してきた。
この時代の代表的名医に華佗〔注:後漢の人:紀元208年に死去〕がいた。
華佗は鍼灸も湯液にも卓越しており、『中藏經』を著したとされる。
その文章内容から華佗の意思を受け継いだ弟子の呉晋または樊阿によって編集されたとする説が有力である。したがって、時代は三国と思われる9)。
3-1 『中藏經』
『中藏經』の中に次のような三焦についての記載がある。
「三焦は人の三元の気であり、中清の府と言われている。五臓六腑・営衛経絡・内外左右上下の気を総領している。三焦を通じて、すぐに内外左右上下にすべてが通じて、全身を灌漑し、内外を調和させ、左より右へ、上から下へと導き、これより大きいものはない。別名を玉海、水道と呼ばれている。」(論三焦虛實寒熱生死逆順脈證之法第三十二)
また、 三焦 の鬱結についても次のように述べている。「人間のあらゆる病気の中で、最も治療が難しいのは水です。 水は腎臓をつかさどるものである。 腎は人間の本質である。 腎が丈夫であれば、水は海に還る。 腎が虚していれば、水は皮膚に分散される。 また、三焦が鬱結し、血と気が従わないので、虚実が変化し、水は気とともに流れる。従って、水病である」。(「論水腫脈證生死候第四十三」)
3-2 『傷寒雜病論(傷寒論)』
『傷寒論』は張仲景(AD150~219)によって著され、「なんらかの原理」にもとずいて構成された、最初の臨床医学書である。「何らかの原理」とは私の推測する限り三焦の概念と思われる。しかし、彼は湯液家であり、三焦の実態については詳しく言及していない。ただ、病気の場所としての三焦(上、中,下焦)の言葉は使っている。
4.六朝から清代
六朝から清代にかけて、三焦に関して多くの仮説が提唱されてきた。
元代では袁淳甫(袁坤厚)の「臓腑間隙説」、明代では虞摶の「腔子説」、張景嶽(岳)の「大嚢説」などがある。
三焦をめぐる議論は一段落し、万人が納得する答えが出るはずであった。 ところが、
東西が収束し始めた清朝末期から、次第に西洋医学が医学の主流になっていった。
5.清代末期から現代
中西医匯通派
十九世紀,中国に西洋医学が流入したことによって,中国伝統医学には,さまざまな変化が生じた。そのうち,西洋医学の概念を伝統医学に積極的に取り入れた人たちを「中西医匯通派」と呼ぶ。唐宗海(1851-1908 字を容川)はその代表的人物の一人である。 彼は、三焦腔子膜説の影響を受け、また当時の西洋医学の知識をそれに結合させて、油脂三焦の説を提唱した。彼は、三焦は水道を通調させる作用があるということに着目し、《医経精義》の中で次のように説明している。「焦は古くは膲と書かれ、身体の隔膜を指し、水をめぐらせるものでした。西洋医学でいう所のいわゆる連網は、隔膜および俗に言われている網油そして身体の膜などのすべてです。このうち網油は膀胱に連なり付着しています。水はこれによって網油の中から膀胱へと滲み入ることができるのです。このことがすなわち古書に、三焦は決瀆の官、水道出づ、とされている理由である。」当時の不十分な解剖学的知識のため、理解できないところがあるが、本質的には大友氏の臓側腹膜説に類似しているのだろうか。
清朝末期、列強が中国に侵攻した。 1919年、五・四運動は、西洋の学問の最高峰である民主主義と科学を全面的に受け入れることを提唱し、古い学問を無駄なものとして扱い、 中国医学もその影響を受けた。 この時期、医師たちは西洋の解剖学・生理学に三焦に相当する用語を見つけようと躍起になり、「百花繚乱、騒然」の様相を呈した。
以下は、2006年時点での中国の三焦の現代医学的見解である10)。
(1) 空腔構造
三焦は「空腔構造」であり、内臓の間隙に存在するという見解で、(1)袁淳甫の「間隙説」(2)虞摶の「 腔子説」(3)張景岳の「大嚢説」に類似している。
(2) 膜状構造
これは唐容川や張錫純が唱えた三焦の「油膜」説に相当している。
黃維三(1986年発表)は、『内経』によれば、三焦は臟腑間の膜膈を指し、油脂與皮裏肉外之腠理,であり、空洞ではないことを指摘した。
陳潮祖(1994年、2004年発表)は「膜腠三焦説」を提唱し、三焦の組織構造は膜原と腠理の二部分からなるとした。筋膜は人の重要組織で 筋(腱)は膜の束であり、膜は筋(腱)の延長である。 少陽三焦の組織構造は、膜原と腠理の2つの部分から構成されている。 膜原は筋(腱)の延長線上にあり、腠理は膜の外側にある組織の間隙で、『内経』では「分肉」と呼ばれている。 膜腠はどこでも、皮膚の裏、肉の外、それから五臓六腑とつながっていて、上は頭頂, 下は足まで、他の五臓が一定の形を持っているのとは違って、どこにでもつながっている。
劉法洲(1999年発表)は、 「腔子三焦説」と「油膜三焦説」がより現実的であり、その中でも「油膜三焦説」が優れているとした。
張效霞(2005年発表)は、「三焦とは、小網、大網、腸間膜のことです。」と述べている。
(3) 網油とリンパ腺、管、節などの有形の組織
張志華ら(18)(2003年発表)は、「三焦はリンパを含むことができるが、リンパは三焦とは言い切れない。 網油説の如く、リンパ腺、管、節などの有形の組織は三焦の組み合わせであると言うのが正しいだろう。」と述べている。
(4) 生理学的分類
(4-1) リンパ系統説:章太炎が提唱した三焦の「リンパ系理論」である。江蘇省江陰縣衛生局中西醫結合科研小組(1974年発表)は、「三焦の本質はリンパ系に似ている 」と述べてる。
しかし、張志華ら(2003年発表)は、「三焦はリンパを含むことができるが、リンパは三焦とは言い切れない。 網油説の如く、リンパ腺、管、節などの有形の組織は三焦の組み合わせであると言うのが正しいだろう。」と述べている。
(4-2) 体液平衡調節系統説
夏涵(1958年発表)は、「三焦は人体の全代謝過程の三段階であり、三焦は特定の臓器や解剖学的部位を指すのではなく、体液バランス調節系を指すと考えられる。」と述べている。
(4-3) 水液代謝系統説
楊蘇民(1959年発表)は、「腎は肺と膀胱をつなぐことができ、この二つの臓器はすべて三焦の働きに依存している。 三焦は肺、腎、膀胱の三臓の間にあり、孤立した三臓を機能的な全体に結びつけ、上から下まで水路を形成し、共に水分の排泄過程を完成させる。 三焦は水の排泄において第一の位置を占めている。」と述べている。
(4-4) 細胞外液説
邱振剛(2004年発表)は、「三焦は様々な組織を含み、皮膚、筋肉、内臓の間のあらゆる場所に存在し、独立して存在し、全身に広がっている。 臓器や開口部を結ぶ組織の大きく複雑なネットワークであり、現代医学でいう体内環境である細胞外液と大きな類似性を持っている。」と述べている。
まさに、この論文が私の言いたい「三焦は間質・間質液」である。
日本でも同様の考えを曺桂植氏が「三焦と間質液スペース」として2017年に発表されている11)。この発表の1年後、これらの仮説を実証するような論文が2018年4)と2021年5)にニューヨーク大学グループから発表された。
いよいよ本論に入りたい。
三焦は間質か
古典的生理学教科書によると、これまで間質は次のように考えられていた。
「体の約6分の1は、細胞と細胞の間の空間であり、これらを総称して「間質」と呼び、これらの空間にある液体が「間質液」である。
間質液の構造を図2に示す。この中には、大きく分けて2種類の固形構造が含まれる:
(1)コラーゲン繊維束と(2)Proteoglycan filaments(プロテオグリカンフィラメント)である。コラーゲン繊維の束は、間質内に長く伸びている。コラーゲン繊維の束は非常に強く、組織の引っ張り強度の大部分を担っている。しかし、プロテオグリカンフィラメントは、約98パーセントのヒアルロン酸と2パーセントのタンパク質からなる非常に薄いコイル状またはねじれた分子である。この分子は非常に薄いため、光学顕微鏡では決して見ることができず、電子顕微鏡でもその存在を示すことは困難である。通常、間質中のほとんどすべての液体は組織ゲルに包まれており、自由にながれている液体(自由液)はほとんどない12)。」
しかし、最新のテクノロジーを駆使して人体の奥深くを観察した結果、驚くべき事実が判明した。それは、これまで知られていなかった自由液とコラーゲンの束のネットワークが、体全体に張り巡らされていたのである。
ニューヨーク大学の研究者らは、これを「間質という新たな器官であり、人体最大の器官である」と2018年3月27日、科学誌『Scientific Reports』に発表した4)。
ニューヨーク大学の研究
新たな間質の発見
彼らは、粘膜下層、真皮、筋膜、血管外膜の解剖学的概念の改訂を提案し、コラーゲンが密に詰まったバリア状の壁ではなく、液体で満たされた間質空間であることを示唆した(図3)。
すなわち、これまで認識されていなかった、組織内や組織間に広く存在する、巨視的な、流体で満たされた空間を発見したのである。このような空間の存在を見過ごしたのは、私たちが顕微鏡下で組織を固定したスライドガラスから見ていたからである。組織を固定すると、液体が失われ、余分な媒体を含まない収縮した細胞や構造物だけが映し出される。この固定による崩壊のアーチファクトは、何十年もの間、体中の液体で満たされた組織タイプを生検スライドで固形に見せてきたのである。
この発見は蛍光色素の注入を検出するための、薄いカメラ、レーザー、センサーを含む、共焦点レーザー内視鏡などの先端医療機器からもたらされた。
最初の発見は、ニューヨークのベス・イスラエル・メディカル・センターで、胆管周辺に広がる癌を調べていた医師が、医学の教科書とは違う、相互につながった空洞に気づいたときである。その画像を従来の生検スライドと比較したところ、その空間は消えていたのである。
しかし、その後、癌の手術を受けた12人の患者を共焦点レーザー内視鏡で検査したところ、空間は事実上、体内の至る所にあることに気づいた。それは真皮に認められ、消化管や気管支、膀胱そして、動脈や静脈、筋膜を囲んだりしている層にも確認できた(図4)。
この組織は強度の高いコラーゲンと柔軟性のあるエラスチンという2種類のタンパク質による格子構造で、体重のおよそ20%に相当する体液が流れている。その流れは、その組織の動き、拍動や蠕動運動により最終的にはリンパ系に繋がる。肝臓の専門家はDisse腔やMall腔を、脳神経の専門家はVirchow-Robin腔とGlymphatic Flowを、整形外科医は筋膜(Fascia)そして鍼灸家は経絡を思い起こすのではないだろうか。
我々、漢方を勉強している者たちにとっては、有名無形の三焦が最新の技術、共焦点レーザー内視鏡で見えるようになった瞬間であった。
ある科学者は「この発見は従来のリンパ系で別に新発見ではない」とコメントするが、問題を整理しよう。
間質とリンパの関係
ヒトの体のなかにはおよそ60%の水分がある。その水分のうち、およそ2/3は細胞内液であり、1/3は細胞外液である13 )。
図5は間質液(組織液)の流れを示している。矢印は血液・間質液・リンパ液の流れ、矢頭は毛細リンパ管の起始部を示す。間質液の80~90%は血管に戻るが、リンパ管に再吸収されるのは残りの10~20%である。
したがって、間質液はリンパ系の上流に位置するが、リンパ系そのものではない。
間質空間の連続性
さらに、2021年にもニューヨーク大学のグループが間質に関する続編を発表した5)。
2018年に発表した論文では、液体でみたされた間質空間が体内で連続しているのか、それとも個々の臓器内に限定されて不連続なのかは、依然として不明であった。
今回、彼らはヒトで、2つのアプローチで間質空間の連続性を示す証拠を示したのである)。
1.刺青色素や銀コロイドの移動
1)皮膚組織においては、美容目的の刺青を含む標本(3人)を調査した。刺青粒子は乳頭状、網状真皮および皮下脂肪膜のコラーゲンネットワークのコラーゲン束の間、すなわち、ファッシアと呼ばれる間質空間に局在した。
銀粒子は、美顔目的でコロイド銀の外用後にargyria(銀皮症)を発症した患者の2つのサンプルでも同様の場所に観察された。また、真皮の付属器、血管周囲外膜、神経周囲にも銀粒子が確認された。
2)悪性ポリープの治療のために、大腸内視鏡検査時および手術前に病変部に隣接する大腸粘膜下層に刺青を注入した。調査した5つの検体すべてにおいて、その刺青粒子は大腸粘膜下層、前膜筋層、腸間膜のコラーゲンネットワークの細胞内および間隙に移動していた。
もう1つのアプローチは、最小の間質空間(すなわち、細胞間や毛細血管周辺)と、最近彼らが発見した大きな線維結合組織空間で、ヒアルロン酸(HA)の分布を調べたものである。
前述したように間質にはコラーゲン繊維束とプロテオグリカンフィラメントがある。
プロテオグリカンフィラメントの分子は非常に薄いため、光学顕微鏡では決して見ることができず、電子顕微鏡でもその存在を示すことは困難である。
しかし、かれらは HA結合タンパク質(HABP)による染色(ヒアルロン酸染色と呼ぶ)で可視化に成功したのである。
- ヒアルロン酸染色で臓器境界を越えた間質空間の連続性を示す
ヒアルロン酸(HA)はあらゆる発達段階において、体中の間質空間に存在する。 HAの物理的特性から、HAは間質内の液体や他の溶質、低分子の流れを調節していると考えられている。
いままでH&E染色で何もないように見える間質空間が、ヒアルロン酸染色することによってHAで満たされていることを証明した。この発見により、間質空間は皮膚、大腸、肝臓の組織区画と筋膜面の間、および血管と神経の周りの線維組織内でHAで連続しており、複数の臓器を通過する可能性があることを証明することができた。
間質空間にある間質液は拡散的に短距離を流れるのは分かったが、血液循環のように体内を循環しているのだろうか?
2006年以降、北京グループは、間質液の輸送に関する一連の研究成果を発表してきた。
中医学とも連携して、飛躍した科学技術を用いて「間質液循環システムの仮説」を証明すべく一連の研究を行っている。
以下はLi Hらが2020年に発表した総説から引用した6)。
北京病院の研究
1.造影MRIによる長距離の間質液経路を可視化
造影MRIなどの空間分解能の高い技術を用い、ボランティアの四肢末端の経穴(通常は鍼)にMRIの造影剤(Gd-DTPA)を皮下注射し、長距離の間質液経路を可視化した。
四肢の長距離の間質液経路には、非平滑な連続軌道を持つ経路と滑らかな連続軌道を持つ経路の2種類を認めた。
1)手や足の注射点がツボではなく静脈血管の近傍にある場合は、滑らかな経路のみが表示された。さらに画像データを解析したところ、滑らかな経路は血管内腔以外の静脈血管の部分的な壁が強調されているようであった。
2)ツボからの滑らかでない経路は皮下組織にあり、”鍼の刺す抵抗 “という特徴を持っていた。
これらの平滑な経路も平滑でない経路も、リンパ管造影で可視化されたリンパ管と一致しなかった。
2. ヒトにおける経穴からの間質経路の解剖学的・組織学的構造について
1)生理的な条件下で、経穴からの長距離間質経路の解剖学的、組織学的構造を調べた。閉塞性動脈硬化症による重度の足壊疽で、右下腿の切断が予定されている被験者を1名募集した。切断の前に、足首の経穴に蛍光トレーサーを皮下注射した。切断から約90分後、下腿の組織サンプルを組織学的に分析した。その結果、足首から切断された下腿部にかけての間質経路は、繊維性結合組織によって4種類に分類できた。
(a)真皮と皮下組織の皮膚経路
(b)静脈外膜(外膜を含む)に沿った静脈周囲経路
(c)動脈外膜(外膜を含む)に沿った動脈周囲経路
(d)神経内の線維内膜-神経周囲-神経上膜経路
これらの結果は、間質液の輸送経路が多形であり、少なくとも4種類の解剖学的分布を持っていることを明確に示している。
彼らは、ボランティアでMRIにより観察された滑らかな経路は血管周囲の経路であり、滑らかでない経路は皮膚経路であろうと推測している。
2)生理的条件に加えて、非生理的条件下での間質液の輸送経路も調査した。
切断後に同じ経穴に蛍光トレーサーを注入された3本の切断下腿が、調査された。これらのケースでは、脚の切断端に血圧計のカフを装着し、収縮期圧力50-60mmHg、圧迫-弛緩回数18-20回/分で定期的に「機械的圧迫」を行った。約90分の操作の後、蛍光染色されたが、前述の同じ4つのタイプが観察された。
以上のように発見された間質液の輸送経路は、生理的・非生理的な条件下で、以下のような判断が可能である。
(a)長距離の間質液輸送経路は、生体または死体において少なくとも4種類の解剖学的構造を含む。(b) 各間質液輸送経路の組織構造は、一貫して繊維性結合組織で形成されており、間質液の流れは全身に普遍的に存在する繊維性マトリックスであることを示唆している。
(c)長距離の間質液輸送のメカニズムはまだ完全には解明されていないが、心臓の拍動や血管の血管運動のように、動力源の往復運動は間質液輸送において極めて重要である。
彼らは、長距距型・間質液輸送の光学的イメージングについても、いくつかの特徴を明らかにした。
二光子共焦点レーザー顕微鏡two-photon confocal laser microscopy(TPCLSM)を用いると、すべての間質経路に数千個の蛍光染色されたミクロンサイズの繊維が存在し、経路の長軸方向に分布していることがわかった。つまり、高度に構造化された間質マトリックスを介した間質液の輸送において、繊維はガイドレール(fibrorail)として、不可欠な存在である。
上記の発見が全身に普遍的に存在することを確認するため、ヒトの遺体を用いて、機械式胸部コンプレッサーを用いた模擬心臓の脈動による間質経路の検証を行った。
親指の第一関節のツボ(少商)に蛍光トレーサーを皮下注射すると、2.5時間の胸部圧迫を繰り返した後、親指から胸壁近くの右心房に至る蛍光染色された間質液経路が可視化された。 親指からの皮膚経路は、手と前腕の真皮、皮下組織、筋膜組織に認められたが、肘窩より上の皮膚には認められなかった。
親指からの間質経路は、腕の静脈、腋窩鞘、上大静脈、右心房上の表在組織に沿って観察された。組織学的およびマイクロCT(より高い解像度)のデータから、これらの長距離経路は血管やリンパ管ではなく、ミクロンサイズの繊維が親指から右心房や付属器の表層組織まで長距離にわたって集合している繊維性結合組織であることが示された。
これらの解剖学的データから、線維性経路の構造的骨格は、ミクロンサイズの線維が縦方向に集合し架橋された多層構造からなり、間質液の流れを方向付ける線維性網を提供していることが検証された。TPCLSMにより、これらの結合組織は、輸送経路の長軸に沿って配向した豊富な蛍光染色繊維で構成されていることが明確に観察された。
- 外皮間質液の流れを生体でイメージングする
ウサギの足首の動脈血管と静脈血管の周囲の間質空間に蛍光トレーサーを注入した。それによって可視化された足首からの蛍光ISFは、血管系の外膜とその周囲の線維性結合組織に沿って、ウサギの心臓の房室溝、前室溝、後室溝に入り、心嚢液を形成した。
- 長距離の連続した間質液の流れは循環しているのか?
古典的生理学によれば、間質液は動脈毛細血管から血漿が濾過されることで生成される。
ウサギを用いた我々のデータから、長距離の外膜のinterfacial dynamic transport(IDT)界面動態輸送経路は、末梢の間質液 を心膜腔に送り込み心膜液を形成し、血管樹に沿って周辺組織に 間質液 を拡散・交換する役割を担っている。同時に、IDT経路からの蛍光トレーサーは下大静脈内の静脈弁を染色することが確認され、蛍光トレーサーが最終的に血液循環に入り込んだことが示された。
外膜IDT経路のトレーサーの行方を蛍光顕微鏡で追跡すると、IDT経路の蛍光間質液が毛細血管網に吸収され、近くの静脈血管に収束していることが容易に判明した。この結果は、1896年にアーネスト・スターリングが発表した毛細血管による間質液の交換の理解と一致する。このように、連続した間質液の流れは、冠動脈の毛細血管を含む長距離IDTシステムのなかの毛細血管を介して血液循環と常に交換し、体内を循環することができる。
考察
ニューヨーク・グループのまとめ
ヒト肝外胆管粘膜下層やヒト真皮の上皮表面から50-70μm下の大きな間質空間を通る流体の流れが報告された。
さらに、他のすべての内臓器官の粘膜下層や皮下筋膜を含む他の繊維組織も構造的に類似していることが示され、同様に流体の流れを支えていると仮定されている。これらの組織では、いずれも直径20-70μmのコラーゲン束のネットワークによって空間が規定されていた。コラーゲン束の多くは、ビメンチンとCD34を共発現する紡錘形の細胞によって裏打ちされていた。
体には、コラーゲン、エラスチン、プロテオグリカンなどの細胞外マトリックス成分からなる網目状のネットワークが、すべての組織や臓器を通じて連続している。また、神経や血管の線維性被覆は、臓器の境界を越えて構造的な連続性を生み出している。彼らはヒトの繊維組織を通る流体の流れを確認したが、これらの間質空間が体内で連続しているのか、それとも個々の臓器内に限定されて不連続なのかは、依然として不明であった。しかし、あらたに2つのアプローチで間質空間の連続性を示す証拠を示した。非生物的粒子(タトゥー色素、コロイド銀)は、結腸と皮膚の間質空間と隣接する筋膜の中まで追跡された。ヒアルロン酸染色によって、間質空間の高分子成分であるヒアルロン酸も可視化された。両手法とも、臓器内および臓器間の間質的連続性を示し、臓器および臓器間の空間を横断する神経周囲および血管外膜内にも間質的連続性をしめした。これらの事実は、分子シグナル伝達、細胞輸送、悪性疾患や感染症の拡散に重要な意味を持つ、液体で満たされた間質空間の体内ネットワークが存在することを示唆している。
北京グループのまとめ
間質液循環システムの仮説
間質空間にある液体は、成人の体重の20%程度を占め、拡散的に短距離を流れる。
しかし、血管循環のように体内を循環しているのだろうか?
2006年以降、研究者たちはボランティアや死体から得たデータから、長距離の間質液の流れ(間質液循環システム)の仮説を提案した。
間質液の流れは、少なくとも4種類の線維性結合織から構成されている。
(a)真皮と皮下組織の皮膚経路
(b)静脈外膜(外膜を含む)に沿った静脈周囲経路
(c)動脈外膜(外膜を含む)に沿った動脈周囲経路
(d神経内の線維内膜-神経周囲-神経上膜経路
それぞれの間質液経路の骨格は、繊維が長軸方向に配列され、流体の流れのためのファイバーレールとして機能している。繊維状経路における流体の移動は、動的な駆動源(心臓の拍動)に応答するものであることを明らかにした。
図6は間質液循環システムの仮説を図式化したものである。
毛細血管の動脈側に由来する間質液は、繊維間のゲル状物質に拡散し、静脈側で再吸収される。これが従来の微小循環における間質液交換の概念である。
一方、間質液はinterfacial transport zone 界面輸送帯(ITZ)に入り、界面液を形成する。界面液(矢印)は、細胞外マトリックスのコラーゲン繊維に沿って輸送され、心拍などの積極的な動的駆動力により輸送される。
コラーゲン繊維は親水性であり、ITZの形成に関与している。
疎水性の弾性繊維にITZが存在するかどうかは、今後さらに解明される必要がある。細胞や血管の間の不規則な間質空間とは対照的に、微細なITZは、流体の流れに制約を与え、整然とした空間を提供する。
ニュヨークグループも北京グループも「間質」という同じものをみているが、前者は微視的、後者は巨視的な見方である。
面白いことに同じ「間質」というテーマにもかかわらず、お互いの文献は引用していない。現実社会の米中対立のようだ。
北京グループは「間質は経絡である」と証明したいようだが、現実では証明しきれていないと思う。2022年には経穴・経絡の観点で論文をだしている14)(データは今回の総論のデータと同じ)。
前述したように、ボランティアの四肢末端の経穴にMRIの造影剤(Gd-DTPA)を皮下注射し、長距離の間質液経路を可視化した。
使用した経穴は手だと大腸経の商陽で合谷を通ることは確認されている。足だと脾系の陰白、肝経の大敦、腎経の太渓の3つのツボに造影剤を注入している。造影された経路は、1つの交点に収束せず、異なる深さの三陰交を通過することがわかった。MRI像も提示されているが、私は静脈と区別がつかなかった。少なくとも、リンパ管造影で可視化されたリンパ管と一致しなかったので、リンパ管ではない。
ツボにトレーサーを注入しても、間質液が静脈に流れこむように、トレーサーは静脈壁や静脈内に認められるのであって経絡ではなさそうだ。もっとも「気」をトレースすることは、今のところできないので、経絡の存在は否定できない。
それとも、この研究は大友一夫氏が推測しているように、「経絡は脈管以外に考えられない」ということを示唆しているのだろうか。
結語
米中の研究で共通する事実は、間質空間にある成人の体重の20%程度を占める液体は、結合織からなる網目状のネットワークの中を流れていることである。それは、コラーゲン、エラスチン、プロテオグリカンなどの細胞外マトリックス成分からなるが、すべての組織や臓器を通じて連続している。近距離ではスターリングの法則により静脈で吸収される。しかし、間質液の遠距離の移動は皮下組織のみならず、臓器内および臓器間の間質、そしてそれらの隙間空間を横断する神経周囲および血管外膜内も含む結合組織の中を流れるのである。それは全身の結合織のネットワークとして働いている。ある人はそれを筋膜(Fascia), 経絡とよび、私は三焦と考える。
文献
1) 山田慶兒 『中国医学はいかにつくられたか』 岩波書店〈岩波新書〉、P94、1999年。
2) 浅野 周 全訳中医基礎理論 (中医薬大学全国共通教材) たにぐち書店
東京 200年8月 p132-135
3) 劉 燕池 (著) 詳解・中医基礎理論 東洋学術出版社 千葉 1997 p92
4) Benias, P. C. et al. Structure and distribution of an unrecognized interstitium in human tissues. Sci. Rep. 8, 4947 (2018).
5) Cenaj, O., Allison, D.H.R., Imam, R. et al. Evidence for continuity of interstitial spaces across tissue and organ boundaries in humans. Commun Biol 4, 436 (2021). https://doi.org/10.1038/s42003-021-01962-0
6) Li H, Yin Y, Yang C, et al. Active interfacial dynamic transport of fluid in a network of fibrous connective tissues throughout the whole body. Cell Prolif. 2020;00:e12760. https ://doi.org/10.1111/cpr.12760
7) 大友一夫.三焦.東静漢方研究室 1980;4(6):1-13.
8) 寺澤 捷年 三焦に関する大友一夫学説の妥当性 日東医誌 2018;69:57-66.
9) 傅 維康 (著), 川井 正久 (訳) 中国医学の歴史 東洋学術出版 市川 1997 p194
10)王元甫 三焦之文獻與研究 南京中醫藥大學研究生畢業論文 2006年 6月
11) 曺桂植 三焦と間質液スペース 中医臨床 38 p62-66 2017
12) Guyton AC. The microcirculation and the lymphatic system: capillary fluid exchange, interstitial fluid, and lymph flow. Textbook Med Phys 9th edition 1994;177-190.
13)加藤征治 新しいリンパ学 金芳堂 京都 2015
14) Li, Hongyi et al. (2021). An acupoint-originated human interstitial fluid circulatory network. Chinese Medical Journal. Publish Ahead of Print. 10.1097/CM9.0000000000001796.