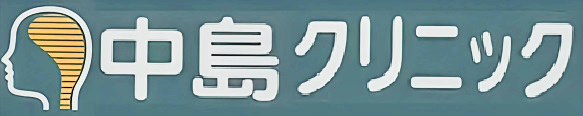緒言:
1980年大友一夫氏は東静漢方研究室誌の論文「三焦 」1)で次のように述べている「三焦の形、語源、位置に関し、古書に則って考察を加えてきたが、それらを整理すると、以下の如きものが想定されてくる。胃からは、水穀の精微をしぼりとる二通りの「布状のもの」が出ており、それが上焦と中焦を表している。 腸管からは、やがて小便となるような水分を吸収する「布状のもの」が出ており、それを下焦と称している。したがって、上焦、中焦、下焦とも、横隔膜下に存在する。この「布上のもの」は現代医学的にみると臓側腹膜が合わさった間膜としている。現代解剖学の俎上に“三焦”を載せるならば 、 その実体は 、 臓側腹膜そのものである」
2018年に寺沢捷年氏は大友説を支持し「腸間膜が一つの臓器である」というCofferyの説2)を基に三焦は腹膜(腸間膜)に対応するとした3)。
腹膜は腹壁内面の壁側腹膜(parietal peritoneum)と臓器表面の臓側腹膜(visceral peritoneum)に区別される。 しかし、壁側腹膜と臓側腹膜は連続しており、その実態は漿膜であり、漿膜面の総面積は1.7~2.0 m2に達する。これは体表の表面積にほぼ等しい。腹膜のみならず、胸膜・心膜の膜はすべて漿膜である。腹腔を覆う漿膜は「腹膜(peritoneum)」、胸腔を覆う漿膜は「胸膜(pleura)」、と呼び、心臓の表面を覆う漿膜は「心外膜(pericardium)と称される。
したがって、漿膜に焦点をあてると、腹膜腔、胸膜腔並びに心外膜腔が三焦ともいえる。
黄帝内経では、胃が氣(衛氣、営氣)の根源である。
したがって、三焦の臨床応用では腹診が必須であり、そのなかでも「心下」は重要な意味をもつ。
「心下」とは西洋医学でいうepigastric regionだが、その痛みは胃潰瘍のみならず、狭心症、肝疾患などの症候をあらわす場合がある。西洋医学では、個々の臓器の疾患は詳しいが、腹腔内壁ならびに腹腔臓器を包む膜にはあまり注意を払ってこなかった。
腹診をするにあたって重要なのは、臓器のみならず、それを包む膜とその間隙, そこを流れる氣と水、すなわち三焦を診ることである。 江部経方医学では胃氣が重要と考え、胸・膈・心下が氣の流れを調節していると考える。したがって、腹診の中でも「心下」の腹診は重要であるので、心下の解剖を中心に考察する。
心下の解剖学
腹壁を開くと、肝臓と胃が存在する。肝左葉を持ち上げると、胃の小弯と肝臓の間に小網という薄が存在している。さらに、胃大弯から垂れ下がる大網が目につく(図1)。
小網、大網とは、腹膜の一部であるが、先ずは腹膜の理解が重要である。
腹膜についてはほぼ同義的に「漿膜(英語:serosa)」という用語が好んで用いられている。
したがって、以下に腹膜を中心に述べるが、腹膜とは漿膜のことを言っている。
腹膜(漿膜)
腹膜は腹壁内面の壁側腹膜(parietal peritoneum)と臓器表面の臓側腹膜(visceral peritoneum)に区別される。 しかし、壁側腹膜と臓側腹膜は連続しており、その実態は漿膜であり、漿膜面の総面積は1.7~2.0 m2に達する。これは体表の表面積にほぼ等しい。
間膜と網
腹腔内臓器は完全に腹膜に包まれている。腹膜内臓器の腹膜被覆は、間膜と呼ばれる腹膜のひだで連続している(図2)。
このうち、胃および十二指腸と他の腹部臓器とを連結する癒合した腹膜のひだを網(ラテン語でomenta(複数)、omentumu)という。網には 大網と小網の2つがある。
一方、腸間膜は胃と十二指腸以外の腹腔内臓器を腹壁から吊り下げ、その神経血管束を固定している。腸間膜は吊り下げる臓器によって名前が付けられる。例えば、横行結腸の腸間膜は横行結腸間膜と呼ばれる。後腹膜臓器は腹膜の後方に位置し、その前面のみが腹膜で覆われている。後腹膜臓器には腸間膜はない。
網(Omenta、omentum)
大網Greater omentum
大網は、その名が示すように、2つの網のうち最大のものである。胃の大弯と十二指腸近位部から伸びるエプロンのような構造をしている。ここから横行結腸、空腸、回腸の上を下方に下降する。その後、後方に折れ曲がり、上行して横行結腸間膜に付着する。大網膜には多量の脂肪が含まれているが、その脂肪量は個人差が大きい。
大網は、腹腔内の壁側腹膜と臓側腹膜が互いに癒着するのを防ぐ。例えば、前腹壁を覆う壁側腹膜と回腸の臓側腹膜が癒着するのを防いでいる。非常に可動性が高く、腸のリズミカルな蠕動運動に伴って腹部内を移動する。また、虫垂のような炎症を起こしている臓器に付着して、その臓器を保護することもある。そのため、大網は「腹部の警察官」と呼ばれることもある4)。また、大網は免疫調節と組織再生において重要な生物学的機能を持つ。
大網の生物学的特性には、新生血管、止血、組織治癒および再生が含まれる。
細胞や組織培養のための生体内インキュベーターとしての役割などがある。これらの特性のいくつかは、長い間外科手術の現場で指摘され、いくつかの手技で経験的に使用されてきた。例えば、脳の血行不全に対して、大網移植術が行われたことがあった5)。
小網(Lesser omentum)
小網は、内側に位置する肝胃間膜と外側に位置する肝十二指腸間膜の2つの間膜からなる。肝胃間膜は、胃の小弯と肝臓の内臓表面とを連結している。肝十二指腸間膜は十二指腸球部から肝臓の臓側表面に向かって伸びている。肝十二指腸間膜の中には肝門脈、肝動脈、胆管が通っている。
さて、この大網と小網によって形成される腹部の閉鎖空間を網嚢(Lesser sac, Omental Bursa)という。
大嚢Greater sacと網嚢 Lesser sac(omental bursa)
腹膜腔は、一つの大きな袋と思われているだろうが、実際は大小二つの袋からなる。大きな袋を大腹膜腔(major peritoneal cavity)という。小さな袋を小腹膜腔(lesser peritoneal cavity)という。
大腹膜腔は大嚢(greater sac)ともいわれ(大網ではないことに注意)、横隔膜から骨盤腔まで伸びている。横行結腸によって2つの区画に分かれている。
一方、小腹膜腔は網嚢(網嚢lesser sac、omental bursa)とも呼ばれ、胃と肝臓、膵臓、脾臓の間にある小さな袋である。網嚢孔(Winslow孔とも呼ばれる)を介してのみ大腹膜腔に連絡している。
この網嚢の存在が腹診における心下の役割に重要な位置を占めると思われるので、詳しく述べる。
網嚢(omental bursa, lesser peritoneal sac)
網嚢は胎生期の腸管回転により胃の後方に陥入した腹膜腔の一部であり、哺乳類にしか認められない。網嚢は大網と小網によって形成され、その前縁は小網lesser omentum,胃十二指腸間膜および胃結腸間膜に,下縁は横行結腸および横行結腸間膜にまた後縁は膵臓により形成され,左外側は脾門部にて盲端に終る。右内側では十二指腸球部のやや上方,下大静脈の前方にて網嚢孔foramen of Winslow により大腹膜腔に連絡している6)。
心下(心窩部)での横断面を(図3)に示す。
正中矢状断をしめすと(図4)になる。網嚢の一部,網嚢上窩(superior recess)は肝の尾状葉を取り囲むように上方に進展し横隔膜に達する。
腹診における網嚢の重要性
腹診における網嚢の重要性を考える。
確かに、心下の直下に網嚢は存在するが腹壁を触診すると、先ずは肝臓そして胃を触れることになる。前述の解剖学で示したように、網嚢は胃と膵臓の間に存在する。指2本ぐらいしか入らない網嚢孔を介してのみ大腹膜と交通する。この部位が三焦の隘路と考えられ、腹膜腔内の流れが停滞しやすい所である。間膜を介して肝臓、横隔膜につながっていることより、腹式呼吸により、パンピング作用で網嚢孔を介して網嚢と腹腔の流れを作っていると思われる。
ちょっとしたことで、網嚢孔は閉じてしまうので、汎発性腹膜炎の場合にも狭い網嚢孔を通して網嚢内に液体貯留がおこることは稀である。しかし,網嚢に隣接した胃あるいは十二指腸後壁の穿孔性潰瘍や膵炎に際しては網嚢内に膿瘍や膵仮性嚢胞が形成される.肝不全などによる大量腹水の場合にも網嚢内にまで腹水が浸入することは稀であるとされるが,癌性腹膜炎や腹膜灌流を受けている患者では網嚢内に大量の液体留貯をみることがあるとされる6)。
これらのことも念頭におき腹診することも重要であろう。
経方医学における心下の所見
腹診は江部経方医学に詳細に書かれているが、心下に関する主なものを見てみよう7)。
傷寒論では、
心下因鞕
心下満而鞕痛 大陥胸湯
心下痛按之石鞕
心下至少腹鞕満於痛
心下痞ー半夏瀉心湯
心下痞鞕ー桂枝人参湯
心下支結ー柴胡桂枝湯
心下逆満、心下有痰飲ー苓桂朮甘湯 などがある。
金匱要略では、かの有名な「心下堅大如盤辺如旋杯」があり、方剤は桂枝去芍薬加麻黄附子細辛湯である。
昨年、ストレスで心下堅大如盤辺如旋杯の腹症を呈した女性の1例を経験した。
当初、何らかの原因で網嚢に体腔液(漿液)が貯留し、胃を押し上げたものと考えた。
しかし、結果は意外なもので滑脱型食道裂孔ヘルニアであった。いずれ、日本東洋医学雑誌に症例報告するつもりである。
漿膜serous membraneの重要性
腹膜を考えるにあたり、重要なことは、前述したように腹膜自体が漿膜であるということである。
漿膜の構造は、どの部位であっても基本的にほぼ同様であり、最表面の基底膜を伴う中皮細胞mesothelial cellと中皮下の疎性結合織で構成されている(図5)。
中皮とは、漿膜の最表面を被覆する単層細胞(中皮細胞)とその直下の少量の結合組織で構成される。中皮下組織には毛細血管とリンパ管が豊富である。漿膜を走査電顕で観察すると小孔stomaが見える。小孔の先にはリンパ槽cysternaがありリンパ管につながっている。したがって、中皮の重要な役割は漿膜を通しての物質と液体の運搬がある。炎症に反応して白血球の遊走の調整や炎症性サイトカインの産生、漿膜修復の成長因子と細胞外物質、凝固と線溶系そして抗体産生の調整を行っている。腹膜中皮の生理学的特性は腹膜透析としてよく知られている。 体腔内には少量の体腔液が満ちており、漿液とも呼ばれている。漿液は臓側と壁側の中皮の間に介在する潤滑液の役割を担っている。生理的に心臓、肺、消化管は常時伸縮や蠕動を繰り返す臓器であり、壁側中皮と臓側中皮は常にこすれ合う状態に置かれている。このような接触を干渉し潤滑にするのが中皮細胞と体腔液(漿液)の役割である8)。
近年の研究では、中皮細胞は臓器表面のバリアとして機能するだけでなく、間葉系細胞の前駆細胞として臓器発生や、臓器表面の創傷治癒にかかわることが明らかになりつつある。ここで、特記しなければならないのは、「中皮細胞は間葉系細胞のマーカーであるビメンチンを発現する」 ということである9)。
2018年ニューヨーク大学グループが、これまで認識されていなかった間質の存在を報告した10)。この構造が粘膜下組織の一部であり、液体で満たされた間質腔であり、リンパ節に流れ込み、厚いコラーゲン束の複雑なネットワークであることが実証された。これこそ、「三焦」の本態ではないかと、現在のところ中医学会、鍼灸医学会の一致した見解である。この構造の詳細は未知であるが、これらのコラーゲン束の片面は、内皮マーカーとビメンチンで染色される線維芽細胞様細胞によって断続的に裏打ちされている。 前述したように、ビメンチンで染色されるということは、間葉系細胞である中皮細胞由来であることを示唆する。したがって、三焦の本態は中皮細胞もしくは間葉系細胞由来と推察される。
次回は、発生学的視点より三焦を考察したい。
結語
1. 三焦の本態は腹膜であるという大友説から、次の仮説が導かれた。
腹膜は中皮細胞よりなる漿膜であることより、三焦は間葉系細胞由来と推察される。
- 心下の腹診において、小網・網嚢の解剖学的重要性を指摘した。
- 腹診は三焦の氣・水の流れを念頭におく必要がある。
文献
1) 大友一夫.三焦.東静漢方研究室 1980;4(6):1-13.
2)Coffey JC, O’Leary DP. The Mesentery: Structure, Function, and Role in Disease. Lancet Gastroenterol Hepatol (2016) 1(3):238–47. doi: 10.1016/ S2468-1253(16)30026-7
3) 寺澤 捷年 三焦に関する大友一夫学説の妥当性 日東医誌 2018;69:57-66.
4) Niamh Gorman MSc. Greater and lesser omentum. https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/greater-and-lesser-omentum
5) Valerio Di Nicola. Omentum a powerful biological source in regenerative surgery
Regen Ther. 2019 Dec 1; 11: 182–191.
Published online 2019 Aug 8. doi: 10.1016/j.reth.2019.07.008
6) Oliveira M. I. et al. Normal anatomy and pathology of the lesser sac.
DOI:10.1594/ecr2011/C-2044
7)江部洋一郎、横田静夫 『経方医学1』第3版 p72, 2011年
8) https://ja.wikipedia.org/wiki/中皮
9) http://hepato.umin.jp/kouryu/kouryu65.html
10) Benias, P. C. et al. Structure and distribution of an unrecognized interstitium in human tissues. Sci. Rep. 8, 4947 (2018).