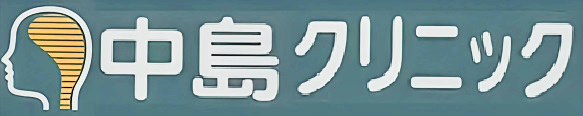はじめに
50年の歴史を誇る『東西漢方研究室』が今年8月をもって廃刊となるそうです。2021年から投稿を始めた私にとって、この雑誌の廃刊は非常に残念です。筆不精の私が毎号締め切りに追われながらも投稿できたのは、中川先生の寛大なご指導のおかげであり、深く感謝しております。
大友和夫氏が1980年に同誌に投稿された「三焦」の論文に触発され、私なりの三焦論を展開してきました。氏は同誌で、次のように述べています。「三焦が臓側腹膜だとしても、また、血や汗や尿に分離する大もとだとしても、傷寒論以後の臨床に役立つわけではない。恐らく、水の通利に関係する生薬のほとんどが三焦に帰経すると唱えても、かえって混乱を来すばかりである」1)。この混沌とした状況の中で、三焦の概念を傷寒・金匱の臨床に積極的に導入したのが、故江部洋一郎氏の『経方医学』です。その核心は「胸・隔・心下」の考えですが、特に「隔」は発生学的に見ると、横隔膜の起源である横中隔ではないかと推測されます。
この最終巻では、三焦を発生学的観点から考察し、「三焦の本態は横中隔ではないか」という仮説を展開します。
緒言
前回、中国医学における三焦という概念は、人体を水系モデルとして捉え、体内を流れる水と気を制御する役割を持つと述べました。人体の大部分は水分で構成されており、その割合は年齢によって変化します。乳幼児では体積の約75%、成人男女では約50〜60%、老年期には約45%まで減少します。一方、胎児の水分含有量は約100%とされています。これを踏まえ、日本では出生前に亡くなった胎児を伝統的に「水子」と呼び、供養が行われています。
水は生命の誕生と進化において極めて重要な役割を果たしたと考えられています。生命の起源に関する諸説の一つに、生命は海から発生したとするものがあります。具体的な環境は不明ですが、潮の満ち引きによってできた「潮だまり」の可能性も示唆されています。水は生命の基本的な化学反応において不可欠な役割を果たしています。溶媒として働き、化学物質を溶かして相互反応を促進するため、生命の誕生に欠かせない要素なのです2)。
今回は、水という視点から発生学を見つめ、三焦を再考します。
三焦論に発生学的視点を初めて導入したのは、イランの医師Majid Avijganだと考えられます。彼は三焦が中胚葉起源であり、胎生期の胚内体腔がその原基であると提唱しました。胎児の発達に伴い、この胚内体腔は心膜腔、胸膜腔、腹膜腔の3つの腔に分化します。Avijganはこれを三焦と解釈しています。さらに、胚内体腔が内臓を覆う膜とも連絡していることから、中国伝統医学や鍼灸の原理も説明できると主張しています3)。
2018年には、ダニエル・キーオンが中医学、主として鍼灸医学を発生学をもとに解説した本を出版しています4)。その中で彼は、三焦は胸膜心嚢膜腔+腹膜腔+後腹膜腔であると述べています。
三焦の原基と考えられる胚内体腔とは何でしょうか。まずは、発生学の基礎から復習する必要があります。 発生学は進歩し、細胞分化の分子的プロセスや形態形成の分子シグナル、そして発生の各段階のタイミングを制御する分子メカニズムの研究は進んでいます。しかし、これらは東洋医学における「氣」と捉え、あえて本論では省略させていただきます。
発生学の基礎
1. 胚盤胞腔という「海」の誕生
卵巣から排卵された卵細胞は卵管内を下降し、12〜24時間以内に精子と受精すると受精卵となります。受精卵は分裂(卵割)を続けながら卵管を子宮に向けて下降し、4日目には桑実胚の状態に発達します。この桑実胚の段階で細胞間に間隙が生まれ、次第に拡大して液体で満たされた大きな腔(胚盤胞腔)を形成し、胚盤胞(blastocyst)へと変化します(図1)。この胚盤胞腔という「海」の中で、胚子が成長していくのです。
1-1 胞胚腔を満たすものは何か
生命や魚類が太古の海から誕生したという考えに基づくと、そこから進化したヒトの胚盤胞腔の組成は海の組成に近いのではないでしょうか。40億年前の古代の海の組成は現在とは異なる可能性がありますが、最近の研究では、多細胞生物のすべての細胞を浸している間質液とあまり変わらないことが示されています。つまり、塩分が多く、Na+イオンとCl-イオンが豊富に含まれているのです2)。
胚盤胞は、胚盤胞腔を囲む栄養膜と、その内側に位置する内細胞塊から構成されています。この内細胞塊が将来、胚子へと発達します。内細胞塊にはヒト胚性幹細胞が含まれており、これらは人体のあらゆる細胞に分化する能力を持っています。胚盤胞腔の壁である栄養膜は、母体の組織とともに胎盤や胎児を包む被膜を形成します。胚盤胞が子宮内膜に接触すると、栄養膜の細胞が増殖しながら子宮内膜内に進入(着床)し、妊娠が成立します。
2. 二層性胚盤(胚盤葉上層と胚盤葉下層)の形成
着床開始後の第2週には、胚盤胞の内細胞塊は胚盤胞腔という「潮だまり」の中で、上皮性の2つの層(胚盤葉上層と胚盤葉下層)に分かれ、2層性の胚盤へと変化します。胚盤葉上層に小さな隙間ができ、この隙間の内側を覆うように胚盤葉上層の一部が上方に伸び、大きな「潮だまり」となって羊膜が形成されます(図2)。
今後、このようにヒトは羊水という水の環境の中で発生・成長します。言い換えれば、胎児は出産まではサカナのように水中生活を続けていくということです5)。
このように、発生の初期段階から胚盤胞腔という生命の根源である海水環境(潮だまり)が形成され、その中でさらに羊膜腔を作り、胚を成長させていきます。以降、この海水環境(潮だまり)を広義の「水」と表現させていただきます。
胚外中胚葉と胚外体腔の発達
栄養膜が発達し胞胚全体が大きくなるにつれ、2層性胚盤から新たな遊走細胞が出現します。この細胞群は羊膜腔と卵黄嚢を外側から包み込み、さらに栄養膜の内面を裏打ちするまでに発達します。この細胞群は胚外中胚葉と呼ばれます。栄養膜の袋が徐々に大きくなるため、胚外中胚葉の細胞間に隙間が生じます。これらの隙間は胞胚の成長とともに拡大し、胚外体腔となり、最終的に羊膜腔と卵黄嚢はこの胚外体腔内に浮かぶ形となります(図3)。つまり、将来胚子となる二層性胚盤は、胚外体腔という大きな水袋の中で、羊膜腔と卵黄嚢という二つの水袋に挟まれて成長していくのです6)。
3. 三層性胚盤の誕生
3-1 胚盤葉上層に原始線条が形成される
受精後3週目(15〜16日目)に入る頃、2層性胚盤の胚盤葉上層を観察してみましょう。羊膜を取り除いて上から見ると、2層性胚盤は頭側が大きく、尾側が小さい洋梨のような形をしています。その中央から尾側に向かって原始線条が確認できます(図4)。原始線条は、胚盤葉上層の細胞が増殖し、これらの細胞群が下層へ潜り込むことで形成される溝状の構造です。
3-2 中胚葉を作る細胞運動
上皮間葉転換(epithelial-mesenchymal transition; EMT)
原始線条において、胚盤葉上層の細胞が増殖すると同時に、上皮としての特性を失い、個々の細胞となって下層へ潜り込んでいきます。この過程により中胚葉が形成されます。
さらに、これらの細胞は胚盤葉下層へと潜り込み、卵黄嚢の細胞と置き換わることで内胚葉となります。中胚葉と内胚葉を生み出した後、残りの胚盤葉上層は外胚葉となります(図5)。
まとめると、原始線条で上層の細胞が非上皮化し、下層へ移動します。胚盤葉下層に移動した細胞は内胚葉に、中間層に移動した細胞は中胚葉になります。移動を終えた残りの胚盤葉上層は外胚葉となります。この現象を上皮間葉転換と呼びます。
上皮間葉転換とは、上皮細胞が間葉系細胞の特性を獲得する現象です。これは初期胚の発生、臓器形成、組織修復時などで見られる重要な過程です。
中胚葉細胞は外胚葉と内胚葉の間を側方や頭方へ進入して中胚葉を形成しますが、原始結節から真っすぐ頭方へ進入する細胞群は「脊索」を形成します。この脊索は背骨の前駆体であり、直上の外胚葉に作用して中枢神経を誘導します。
これまでの過程を原腸形成と呼び、発生において非常に重要です5)。
4. 原腸形成
「出生でも結婚でも死でもなく、原腸形成こそが、人生で真に最も重要な時である。
ルイス・ウォルパート 」7)
二層性胚盤から三層性胚盤が形成される過程を、発生学では原腸形成と呼び、これは画期的な出来事です。原腸形成によって腸ができ、すべての器官を形成していく三胚葉が確立されるのです。
重要なのは、完成した三層性胚盤の3層―外胚葉、中胚葉、内胚葉―がいずれも胚盤葉上層に由来することです8)。
- 中胚葉の変化と重要性
5-1 中胚葉の3部域化(沿軸中胚葉、中間中胚葉、側板中胚葉)
18日目頃の三層性胚盤では、中胚葉組織は脊索の両外側に一様なシート状を形成しています。19日目頃に原腸形成が完了すると、胚中胚葉は沿軸中胚葉、中間中胚葉、側板中胚葉の3つの領域に分化します。発生が進むにつれ、左右の側板中胚葉内に間隙が生じ(図6A)、これらが合体して空洞を形成し、胚内体腔となります。この過程で側板中胚葉は、外側の壁側板中胚葉と内側の臓側板中胚葉に分かれます(図6B)9)。
5-2 胚内体腔
その後、正中線の左右に位置する胚内体腔は頭側に広がり、発育中の心臓管と横中隔の間で合流・融合し、馬蹄形の胚内体腔を形成します(図7)10)。
ここで特筆すべきは、横中隔、心臓管、そして胚内体腔の存在です。横中隔と心臓管の間の胚内体腔は心膜腔となり、横中隔は心臓の形成を誘導する重要な役割を果たします。
受精後約24日目には、発達する脳による胚の折れたたみ現象により、胚子は動物らしい形態を呈し始めます。
羊膜腔が胚子を取り囲むのと並行して、卵黄嚢も細くなり、原始腸管、卵黄腸管、卵黄嚢の3部に分かれます。同時に、体表外胚葉の縁が正中線に沿って融合していくことで、将来の胚内体腔が形成されます(図8)6)。
この胚内体腔は後に心膜腔、胸腔、そして腹腔となりますが、Majid Avijganらはこれを三焦ではないかと提唱しています。
5-3 横中隔と横隔膜
第4週には、3つの壁が形成され、体腔が心膜腔、胸膜腔、腹膜腔に分かれます。最初に形成される壁は横中隔です。これは中胚葉組織が腹側に作る楔形の塊で、体腔を胸部の原始心膜腔と腹部の腹膜腔に分割します。頭部の屈曲と、頭部・頸部の成長差により、この中胚葉の塊である横中隔は、胚盤の頭側縁から尾方へ、将来の横隔膜の位置まで移動します。この過程で、横中隔は肝臓などの器官形成を誘導します(図9A)。
冠状面に形成される胸心膜ヒダ(pleuropericardial folds)は、一時的に原始心膜腔の外側壁に見られますが、正中に向かって成長し、両側のヒダと前腸中胚葉の腹側表面が癒合します。その結果、原始心膜腔が最終的な心膜腔(pericardial cavity)と2つの胸膜腔(pleural cavities)に分かれます。この胸膜腔は、当初、横中隔の背側で1対の心腹膜管(pericardioperitoneal canals)を介して腹膜腔と交通しています。
しかし、胸腹膜(pleuroperitoneal membranes)が背側の体壁から腹側に向かって横断的に成長し、横中隔と癒合することで、心腹膜管は閉鎖されます。こうして横中隔と胸腹膜は、将来の横隔膜の主要部となります。胎児期の8週目から10週目の間に、横隔膜は胚の4つの構造から形成されます。すなわち、横中隔、胸腹膜、沿軸中胚葉からなる体壁(体壁の筋肉の成長)、そして食道の間葉です(図9B)。
考察
現代医学は、脳神経や血液循環の解剖生理、病態理解、治療において、東洋医学を大きく凌駕しています。しかし、リンパ系や間質液の流れに関しては、まだ研究途上にあると言えるでしょう。一方、中国医学では、身体を水系モデルとして捉え、体内を流れる水を重視してきました。さらに特筆すべき概念として「氣」があります。「氣」も水と共に流れると考え、この思想の延長線上に三焦という概念が位置づけられます。つまり、三焦は氣と水を制御する役割を担うとされているのです。ここでは、三焦の概念を発生学の視点から考察してみましょう。
図10は、胎生4週の胚の模式図で、脳神経系と心循環器系を意図的に省略しています11)。この図は横中隔、胚内体腔(心膜腔、2対の胸膜腔、腹膜腔)、そして原始腸管を表しています。横中隔は、胚内体腔を3つの体腔に分ける最初の隔壁となるだけでなく、胚内体腔内に心臓・肝臓・肺などの形成を誘導します。このことから、横中隔が三焦の起源ではないかという仮説が浮かび上がります。すなわち、胚内体腔という「水」と、臓器を誘導する「氣」をコントロールする横中隔が、三焦の本態であるという考えです。
ヒトを含む脊椎動物が海から陸上に進出する際、海の環境を胚内体腔に取り込み、成長・進化してきたと考えられます。死産で生まれた「水子」を見て、古代の人々が「人間の体は水でできている」と考えたのも不思議ではありません。
体内の血液は血管を流れますが、体内の水はどこを流れるのでしょうか?
それは、体の隅々を流れる間質です。2018年、ニューヨーク大学の研究グループは、これまで認識されていなかった間質の存在を報告しました。この構造は粘膜下組織の一部であり、液体で満たされた間質腔で、最終的にリンパ管に流れ込む厚いコラーゲン束の複雑なネットワークであることが実証されました12)。さらに2021年、彼らはこれらの間質空間が体内で連続しており、臓器内および臓器間のみならず、臓器および臓器間の空間を横断する神経周囲および血管外膜内にも存在することを示す証拠を提示しました13)。
三焦の本態は間質か
現在、中医学会や鍼灸医学会では、ニューヨーク大学のグループが示した「間質」が三焦の本態ではないかという見解で一致しています。この構造の詳細はまだ完全には解明されていませんが、重要な特徴が明らかになっています。
間質は、コラーゲン束から構成されており、その片面には特殊な細胞が断続的に存在しています。これらの細胞は、内皮マーカーとビメンチンという二つの指標で染色されることから、線維芽細胞に似た性質を持つことが示唆されています12)。
特に、ビメンチンで染色されるという事実は、これらの細胞が間葉系細胞の特徴を有していることを示しています。間葉系細胞は、発生学的に中胚葉に由来し、様々な組織に分化する能力を持つことで知られています。
この発見は、三焦の構造と機能に関する新たな理解をもたらす可能性があります。また、この知見は中医学や鍼灸医学の理論と現代医学の知見をつなぐ重要な橋渡しとなる可能性も秘めています。
間葉系細胞とは何か
動物の体は上皮と非上皮の細胞で構成されています。上皮細胞は互いに密着して動かないのに対し、非上皮細胞は体内を自由に移動する遊走性が特徴です。
発生学的に、非上皮細胞は主に中胚葉から生じますが、外胚葉の特殊構造である神経堤からも少量の間葉組織が生成されます。このため、これらの細胞を単に中胚葉由来と呼ぶのは不十分であり、上皮の間を埋める組織という意味で「間葉組織」と称しています(医学分野では「間葉」、生物学分野では「間充織」と呼ばれます)6)。
間葉は発生学的に中胚葉から最初の「スープ」として現れます。この「スープ」は間葉細胞、漿液、そして多様な組織タンパク質で構成されています。漿液には、ナトリウムや塩化物など、典型的な多くの成分が含まれており、生命の起源である潮だまりを想起させます。
つまり、間葉組織(Mesenchyme)または間葉系結合組織は、主に中胚葉から発生した胚内の未分化な疎性結合組織の一種です。これは、タンパク質と液体の網目構造(細胞外マトリックス)に埋め込まれた緩い細胞で構成されています。間葉組織は個体発生の初期に生じる非上皮性組織で、突起で連絡し合う細網線維細胞および未分化細胞の緩やかな集合体と、それらの間を満たす細胞間物質によって特徴づけられます。間葉組織は緩い液体状であるため、細胞が容易に移動でき、動物の胚および胎児期における形態構造の起源と発達に重要な役割を果たします。
間葉系細胞は、体の結合組織の大部分を直接生成し、骨、筋肉、脂肪、血管、リンパ系、心臓、腎臓などの多様な組織を形成する能力を有しています。さらに、これらの細胞は細胞間コミュニケーションを促進する重要な役割を担っています。成長因子やシグナル分子を産生することで、細胞間の情報伝達を調節し、組織の成長、修復、再生を促進します。加えて、間葉組織と上皮組織との相互作用(上皮間葉転換)を通じて、体内のほぼすべての臓器の形成に寄与しているのです14)。
三焦の本体は間葉系細胞か
間葉組織は主に発生過程における一時的な組織(移行組織)です。形態形成に不可欠ですが、成体ではほとんど見られません。ただし、例外があります。間葉系幹細胞は、骨髄、脂肪組織、筋肉、乳歯の歯髄に少量存在しています。中国の研究者・安星燕は、この間葉系幹細胞が「三焦」の起源である可能性を提唱しています15)。
発生学的視点から三焦を考察したのは、イランの医学者Majid Avijganが最初であると思われます。
Majid Avijgan説
320年前に書かれたイランの伝統医学(ITM)の資料の一つ、Tebbe Akbari(820年前のITM古文書Asbab va Alaemのペルシア語訳)の第20章で、Hakim Mohammad Akbar Arzaniはメラケ(Meraque)について説明しています。メラケは体中に連絡する間質空間を指すと思われますが、Majid Avijganはメラケと三焦が類似した空間概念に基づくと考えました。2015年、Avijganはこの概念を発生学的に考察し、「三焦は発生初期の胚内体腔である」と発表しました3)。彼は三焦が中胚葉起源であり、胎生期の胚内体腔が三焦の原基だと提唱しました。胚の発達に伴い、胚内体腔は心膜腔、胸膜腔、腹膜腔の3つに分かれ、これを三焦と考えました。発生学的に、胚内体腔は内臓を覆う膜と真皮および皮下組織とも交通しているため、中国伝統医学や鍼灸の原理も説明できると主張しています。
胚内体腔の生理
胚内体腔の内腔壁はすべて漿膜に覆われており、心膜腔・胸腔・腹膜腔の内腔壁も同様です。腹膜は腹壁内面の壁側腹膜(parietal peritoneum)と臓器表面の臓側腹膜(visceral peritoneum)に区別されますが、これらは連続しており、本質的には漿膜です。漿膜面の総面積は1.7~2.0 m²に達し、これは体表の表面積にほぼ匹敵します。
漿膜の構造は、部位に関わらず基本的に同様で、最表面の基底膜を伴う中皮細胞(mesothelial cell)と、その下の疎性結合織で構成されています。漿膜の重要性については、前号「心下は三焦の窓か」で詳述しています16)。
漿液の重要な機能の一つに「物質と液体の運搬」があります。 中皮下組織には豊富な毛細血管とリンパ管が存在します。走査電子顕微鏡で漿膜を観察すると、小孔(stoma)が見られ、その先にはリンパ槽(cisterna)があり、リンパ管につながっています。中皮の主要な役割は、この構造を通じて物質と液体を運搬することです。さらに、炎症への反応、漿膜修復、凝固と線溶系、抗体産生の調整も行います。腹膜中皮のこの特性は、腹膜透析に応用されています。
胚内体腔の連続性
胚内体腔は側板中胚葉内に亀裂が走り、小腔ができ、それらが融合して折りたたまれ、外側縁が正中で合わさることで形成されます。心膜腔・胸膜腔・腹膜腔は一つの胚内体腔から横中隔を中心とした隔壁の発生で分かれるため、もともと連続性があります。
胚内体腔と皮膚との連続性
皮膚では、外胚葉から表皮が、壁側中胚葉から真皮を含む皮下組織ができます。壁側中胚葉は胚内体腔の内腔壁であるため、真皮と皮下組織は胚内体腔と連続しています。
この重要な点を、図11を用いて再度説明します。
中胚葉は、外胚葉と内胚葉の間に位置する間葉系細胞の集合体です(図11A)。その後、中胚葉の最外側にある側板中胚葉は、外胚葉の下に位置する壁側板中胚葉と、内胚葉に密接に関連する臓側板中胚葉という2つの細胞層に分かれ、胚内体腔を形成します(図11C,D)。壁側板中胚葉は体壁の内表面を覆う漿膜に、臓側板中胚葉は腸管を包む漿膜になります。
発生がさらに進むと、側板の最外側部分が外胚葉と共に最終的に腹側正中線で閉じます。壁側中胚葉は体の外壁を形成し、臓側中胚葉は内臓を形成するために発達します。臓側中胚葉と壁側中胚葉の間の空間が胚内体腔となります。壁側中胚葉は胚内体腔の壁であると同時に、真皮を含む皮下組織でもあることがわかります(図C,D)。つまり、胚内体腔と皮下組織には潜在的な連絡があるのです17)。
この連絡の具体例として、皮下気腫という病態が挙げられます。胸膜に穴が開くだけでなく、腸穿孔の場合でも顔面を含む全身に皮下気腫が発生します。大腸内視鏡検査中に結腸穿孔を起こし、気胸、縦隔気腫、縦隔偏位、広範囲の皮下気腫をきたした症例のレビュー報告もあります18)。
このような皮下気腫は、三焦の通路の具体的な例と言えるでしょう。
横中隔という間葉組織集団の重要性
三焦が間葉系組織である間質や胚内体腔に関連していることは理解できましたが、これらは単なる水路や池のようなものにすぎません。中国医学における三焦の意義を深く理解するには、『素問‧靈蘭秘典論第八』の「三焦者.決涜之官.水道出焉」を詳しく解釈する必要があります。
中国は黄河、長江をはじめとする無数の河川が流れる国で、古来より水害に悩まされてきました。そのため、治水能力は国家指導者の力量を測る重要な尺度となってきました。夏朝(紀元前1900年頃)の創始者である禹皇帝は、黄河の治水に成功し、”治水の神様”と呼ばれる伝説的人物となりました19)。禹皇帝は、黄河の氾濫に苦しむ人々を守るため、単に堤防を築くだけでなく、運河を造って水を流すという画期的な治水方法を実施しました。この手法は「決瀆」と呼ばれ、人体における三焦の働きに例えられます。
古代中国では、人体を自然現象になぞらえて理解していました。病気の一因は、水害のように体内の水分調節が乱れることだと考えられていたのです。この水系モデルでは、洪水時に水門を開いて水を放出し、村や都市を守ります。この重要な役割を担う役人が「決瀆之官」です。人体においては、この役割を三焦が果たします。つまり、三焦の主な機能は、全身を巡る水と気を適切に制御することなのです。
発生学を胚内体腔という水の視点から眺めると、横中隔という間葉組織集団の重要性が浮かび上がってきます。
胎生19日目頃に原腸形成が終わると、側板中胚葉の先端に横中隔が出現します。続いて、左右の壁側板中胚葉に小さな独立した空間ができ、後にそれらが融合して左右の胚内体腔を形成します。同時に、臓側板中胚葉には「血島」ができ、将来毛細血管となります。その頭側には心臓形成領域が出現し、後に心臓が形成されます。横中隔は心臓形成領域、胚内体腔、そして中枢神経系の頭側に位置することから、その重要性が推察されます。
横中隔と心臓の発生
横中隔が最初に誘導するのは、ヒトを含む脊椎動物で最初に形成される臓器、すなわち心臓です。
胎生3週間頃、杯盤の頭側に形成された胚内体腔(後の心膜腔)に接するように、中胚葉の心臓形成領域に将来心臓となる2本の毛細血管が出現します。これらの毛細血管は1本の原始心臓管となり、原始心臓管は心膜腔(胚内体腔由来)に潜り込んで心臓へと発達します。胎生約22日頃には心臓が拍動を開始し、母体からの酸素や栄養を全身に循環させます(図12)。
続いて、原始腸管から肺芽が胸腔内で発生し、胎生28日頃には原始肺胞が形成されます。肺胞の形成は8歳まで続きます。胎生32日頃には原始腸管から肝細胞索、胆嚢憩室、膵芽が出現します。これらすべては、漿膜で覆われた胚内体腔の中で横中隔の誘導によって起こります。
横中隔と肝の発生
横中隔と原始心臓管は、杯盤の折りたたみ運動と脳の発達に伴い、口咽頭膜と卵黄嚢の間に移動します。ここで横中隔はさらに肝臓を誘導し、横隔膜の主要部分へと発達していきます。
肝臓の原基である肝芽は、原始腸管の上皮細胞から横中隔という間葉組織集団の中に潜り込み、発達・成長します。肝臓の形成が進むにつれ、横中隔の組織の大部分が肝臓内に取り込まれます。その結果、横中隔で心臓の直下にあったわずかな領域だけが肝臓形成から取り残され、横隔膜の腱中心へと変化します。同時に、横中隔の表層部にあった組織は、肝臓を包む被膜や、肝臓を腹腔に固定する靭帯、被膜状の組織へと変化します。具体的には、肝臓を横隔膜や前腹壁につなげる間膜(肝鎌状間膜、肝冠状間膜、三角間膜)、肝臓の表面を包む被膜、胃の小弯とつなぐ間膜(小網)となります。これらは前号で「心下は三焦の窓か」として発表しました16)。
つまり、横中隔は心臓だけでなく肝臓、胆嚢、膵臓も誘発し、将来横隔膜となって胚内体腔を心膜腔・胸膜腔・腹膜腔に分けるのです。間質の流れは、横隔膜の呼吸運動だけでなく、心膜腔内の心臓の拍動、胸膜腔の肺の膨張・収縮運動、そして腹膜腔内での腸の蠕動運動が駆動力となると考えられます。したがって、私は三焦の本体は横中隔ではないかと推察しています。
三焦の本態は横中隔か
横中隔(Septum transversum)は、心臓と同様に胚発生の過程で形成される重要な構造物です。前述のように、元々は胚盤の頭側縁にある中胚葉の塊で、胚の発達に伴って尾方へ移動し、将来の横隔膜の位置まで到達します。横中隔は胚発生中に存在する一過性組織で、心臓、肝臓、膵臓腹側など様々な臓器または臓器予定領域に隣接しています。特に心臓と肝臓の両方の発達に関与する重要な組織です(図13)。
横中隔は心外膜前駆細胞の供給源としてだけでなく、様々なシグナル伝達成分の供給源としても重要な役割を果たします。例えば、哺乳類の肝臓発達では、心臓中胚葉と横中隔間葉に由来する線維芽細胞増殖因子(FGF)や骨形成タンパク質(BMP)などのシグナル伝達分子を介して、腹側内胚葉から肝臓の誘導が始まります。肝臓発生の誘導後、肝芽細胞近くの横中隔は、肝芽細胞の成長と生存の調節に重要な役割を果たします。このように、横中隔は心臓や肝臓などの周辺臓器の形態形成に重要な役割を果たしていますが、横中隔自体の形態形成の分子メカニズムはまだ明らかになっていません20)。
横中隔と膈の三層構造
図14は「横中隔の三層構造」と江部経方医学の核となる「胸・膈・心下の膈の三層構造」を比較したものです。
横中隔の三層構造(図14A)
横中隔は頭側から次の3層に分かれています:
- 最も頭側の層は線維性の心膜を形成します。
- 中間層は横隔膜筋、横隔膜の中心腱、横隔膜を覆う胸膜と腹膜の中央領域を形成します。
- 最も尾側の層は肝臓の線維性被膜と結合組織、および発達中の中腸の腹側腸間膜を形成します。これが後に小網、網嚢となります21)。
膈の三層構造
江部経方医学の核心である「胸・膈・心下」は、一つのまとまった機能単位を形成しています。そのうちの膈は、上膈・中膈・下膈からなる三層構造を持ち、外殻における皮・膜一腠理・肌という三層構造に対応しています。具体的には、上膈と皮、中膈と膜一腠理、下膈と肌が対応するとされます(図14B)。中膈は外殻の腠理と機能的に連動し、皮・肌を隔てる膜がこの膈と腠理を繋ぎ媒介しています22 p.25–27)。膈のこの三層構造により、皮氣・肌氣という二種類の衛気が外殻へ出入りする経路がより詳細に特定されることになります22 p.38–43)。
さらに、上・中・下の膈の三層構造には、それぞれ生薬の麻黄、柴胡、桂枝が対応するとされています。
それぞれの例を『金匱要略・瘧病脈証并治第四』の処方で挙げています(ちなみに瘧(ギャク)とはマラリアのことです)。
麻黄については、金匱・瘧病にある外治秘要方「牡蛎湯:治牡瘧」の処方構成が、牡蛎四両、麻黄四両、甘草二両、蜀漆三両となっています。この麻黄は上膈の瘧邪を外達させるものです。 白虎加桂枝湯および柴胡桂枝乾姜湯における桂枝は下膈の瘧を外達させます。柴胡は瘧病の治療において重要な生薬であり、その作用は中膈を主としつつ、上・下膈にも及ぶとされます23)。
横中隔の三層構造と膈の三焦構造を比較すると、いくつかの類似点が浮かび上がります。江部の上膈は横中隔の頭側の繊維性心膜であり、胸膜とつながります。中隔は上膈と下膈を分ける膜、下膈は肝臓の線維性被膜と結合組織、および発達中の中腸の腹側腸間膜を形成します。これが後に小網、網嚢、すなわち心下とつながります。江部の「胸・膈・心下」とは横中隔を念頭に置いたものであり、横中隔が三焦の源基であるという仮説を支持するものと思われます。
最後に、江部は彼の著書『経方医学』の総論で三焦について次のように述べています。「中医学でいうところの三焦とは、血脈以外の氣津が循環している場を総称しているものです。具体的には、本章で述べた胸・膈・心下、皮氣、肌氣、脈外の気の経路、腠理、さらには直達路なども三焦を構成しています。したがってこの総論は、ある意味で『三焦論』ということができます」22 p.55)。
結語
2015年、イランの医学者Avijganは、三焦が胎児期の「胚内体腔」に相当するという仮説を提唱しました。胚内体腔とは、発生初期に中胚葉が分かれてできる大きな空間であり、液体で満たされ、その内側は全て漿膜で覆われています。
この胚内体腔は、胎児の体において重要な3つの役割を果たします。まず、心臓、肺、消化管などの内臓が発生する「場所」を提供します。液体に浮かぶことで、臓器は自由に成長することができます。次に、体液の流れによって栄養と老廃物の運搬を行い、後の血管やリンパ管の発生につながっていきます。
特筆すべきは、この胚内体腔の壁を形成する組織(壁側中胚葉)が、同時に皮膚の真皮や皮下組織も形成するという点です。この発生学的特徴は、体腔と体表が潜在的に連続していることを示唆しています。実際、この連続性は臨床的にも確認されており、胸腔や腹腔の損傷時に全身性の皮下気腫が生じ得ることからも裏付けられます。
2018年、ニューヨーク大学の研究グループは、体内全域に広がる新たな水分通路として「間質」の存在を報告しました。この間質がビメンチン(中胚葉マーカー)で染色されることから、その本質が「間葉組織」であることが明らかになりました。
間葉組織は、主に中胚葉に由来する未分化な疎性結合組織です。タンパク質と液体による網目構造の中に細胞が疎に配置される特徴を持ち、多彩な機能を有します。間葉系細胞は骨、筋肉、脂肪、血管、リンパ系、心臓、腎臓など多様な組織への分化能を持つだけでなく、成長因子やシグナル分子の産生を通じて細胞間相互作用を制御し、組織の成長、修復、再生にも寄与します。
胚内体腔の形成と分化を制御する鍵となる構造が「横中隔」です。この横中隔は哺乳類で初めて出現する重要な間葉組織集団であり、胎生18-19日という極めて早期に胚子最先端部に出現します。発生過程において、横中隔は3つの重要な役割を果たします。第一に、心臓、肺、肝臓、胆嚢、膵臓といった主要臓器の発生を誘導する組織誘導の中心として機能します。第二に、胚内体腔を心膜腔、胸膜腔、腹膜腔という3つの独立した体腔へと分画します。そして最終的に、呼吸運動に不可欠な横隔膜へと分化します。このように横中隔は、初期発生から器官形成、さらには生後の生理機能に至るまで、生命維持に欠かせない重要な構造として機能し続けます。
これらの知見を総合すると、三焦の本態は「横中隔」という特殊な間葉組織である可能性が高いと考えられます。横中隔は、胚内体腔という「水」の場を制御し、主要臓器の発生を「誘導」するという二重の機能を有するからです。この概念は、中医学の古典『霊枢』における「三焦者,決涜之官,水道出焉(三焦は決瀆の官であり、水道はここから出る)」という定義とも見事に整合します。さらに、この発生学的知見は、江部経方医学で提唱される「胸・膈・心下」という機能的単位の構造的基盤となる可能性も示唆しています。
謝辞: 本論文の執筆にあたり、ご高閲を賜りました中川良隆先生に心より感謝申し上げます。
文献
1) 大友一夫.三焦.東静漢方研究室 1980;4(6):1-13
2) Interstitial Fluid (ISF- The Internal Sea for life)
https://universe-review.ca/R10-89-ISF.htm
3) Avijgan Majid et.al. Meraque or Triple Energizer (San Jiao):Actual or Virtual Organ in Traditional Medicine – A Hypothetical Viewpoint. Integr Med Int 2015;2:9–20 20 DOI: 10.1159/000433537
4)ダニエル・キーオン (著), 建部陽嗣 他 (翻訳), 閃めく経絡―現代医学のミステリーに鍼灸の“サイエンス”が挑む! 医道の日本社、神奈川、 2018年
5) 岡 敦子 ミニマル発生学 p60-61 医学書院 東京 2023年
6) 山科正平 カラー図解 人体誕生 講談社 ブルーバックス B-2112 東京 2019年
7) Jamie A. Davis 橘 朱美 人体はこうしてつくられる 紀伊国屋書店 東京 2018年
8) WilliamJ. Larsen 相川 英三他 ラーセン最新人体発生学 第2版 学生版 西村書店 東京 2003年
9)Coelomic cavities Chapter 10 Coelomic cavities https://veteriankey.com/coelomic-cavities
10) TL Selvakumari Essentials of Anatomy for Dental Students Development of Human Embryo New Delhi, India、2018
11) G.Prabavathy, Development of Cardiovascular system https://www.slideshare.net/slideshow/cvs-i/58406531#5
12) Benias, P. C. et al. Structure and distribution of an unrecognized interstitium in human tissues. Sci. Rep. 8, 4947 (2018).
13) Cenaj, O., Allison, D.H.R., Imam, R. et al. Evidence for continuity of interstitial spaces across tissue and organ boundaries in humans. Commun Biol 4, 436 (2021). https://doi.org/10.1038/s42003-021-01962-0
14) Kate MacCord, “Mesenchyme“. Embryo Project Encyclopedia ( 2012-09-14 ). ISSN: 1940-5030 https://hdl.handle.net/10776/3941
Published on The Embryo Project Encyclopedia (https://embryo.asu.edu)
Mesenchyme [1] By: MacCord, Kate
15) 安星燕 他 生物学研究诠释三焦器官 / 间充质组织系统的医学实质 基础医学与临床 2018,38:1599-1605.
16) 中島啓次 私の三焦論(3)ー心下は三焦の窓かー 東静漢方研究室 2024;7(1):11-20
17) N.Funayama et al., (1999). Coelom formation: Binary decision of the lateral plate mesoderm is controlled by the ectoderm. Development (Cambridge, England). 126. 4129-38. 10.1242/dev.126.18.4129.
18) Abdalla S, Gill R, Yusuf GT, Scarpinata R. Anatomical and Radiological Considerations When Colonic Perforation Leads to Subcutaneous Emphysema, Pneumothoraces, Pneumomediastinum, and Mediastinal Shift. Surg J (N Y). 2018 Feb 22;4(1):e7-e13. doi: 10.1055/s-0038-1624563. PMID: 29479562; PMCID: PMC5823697.
19) https://ja.wikipedia.org/wiki/禹
20) Saito Y, Kojima T, Takahashi N. Mab21l2 is essential for embryonic heart and liver development. PLoS One. 2012;7(3):e32991. doi: 10.1371/journal.pone.0032991. Epub 2012 Mar 8. PMID: 22412967; PMCID: PMC3297618.
21)The Body Cavity and Wall https://aneskey.com h/the-body-cavity-and-wall/
22) 江部洋一郎、横田静夫; 経方医学1(第3版)、p55 東洋学術出版社、千葉県、2011
23) 江部洋一郎, 横田静夫; 膈と小柴胡湯証、中医臨床、19(1) 56-62, 1988